鉄路に生きた生涯-中野洋前委員長が語る動労千葉の歴史と闘い
 中野洋前委員長は、1940年2月に東京都旧本郷区に生まれる。44年には母親の実家のある千葉県勝浦市に疎開し、少年期を過ごすことになる。父親は44年に召集されて戦死し、保母をしていた母親に育てられる。
中野洋前委員長は、1940年2月に東京都旧本郷区に生まれる。44年には母親の実家のある千葉県勝浦市に疎開し、少年期を過ごすことになる。父親は44年に召集されて戦死し、保母をしていた母親に育てられる。
幼少の頃から活発な性格で、千葉県一の進学校であった千葉一高(現在の千葉高)に進学し、勉学のかたわら、相撲部に在籍した。
高校卒業後、多くの同級生たちが大学に進学する中で、国鉄に就職する道を選ぶ。1958年に臨雇として採用され、勝浦機関区に配属になる。採用後、すぐに動労(動力車労働組合)に加入するが、当時の動労千葉地本は、非常に右翼的な体質の強い組合だった。
ちょうど、60年安保闘争や三池闘争など階級闘争が新たなうねりを開始する中で、早くから労働運動の世界に飛び込み、動労千葉を形成する戦闘的な千葉地本に変革していく闘いの先頭に立つ。それから半世紀にわたる労働運動人生を歩む。
●【1】戦後労働運動を乗り越える視点
中野前委員長は、マルクスやレーニンの著作を学ぶと同時に、産別会議の日本共産党フラクの責任者だった斎藤一郎(49年に離党)の『戦後労働運動史』などの著作を読みあさり、戦後労働運動をいかに乗り越えるかという問題意識を早くから持ち続けていた。
中野前委員長は、2000年に発行された『戦後労働運動の軌跡と国鉄闘争』(以下、『軌跡』と略)で、重要な視点を提起している。
「労働運動史というのは、客観的に一つ一つの闘いを見つめ、評価し、教訓化しなければならない面があると同時に、極めて党派的に見ていかなければならないということがあります。いまわれわれは、大失業と戦争の時代において、闘う労働運動の新しい潮流をつくろうといっている。つまりたいへん厳しい情勢がきている中にあって、総評労働運動が解体した今日、それをいかにのりこえる労働運動をつくりあげていくのかという立場から、戦後労働運動史を見るということが必要なのであって、なにか一般的に歴史をながめるというのではだめだということです」
「より正確にいえば、日本の労働運動全体、日本の階級闘争、日本の革命運動全体を常に視野に入れて、自分たちの産別の闘いも進めるということです」
「つまり、日本の労働運動全体の戦闘化というか、階級的労働運動を再び奔流のごときものにしていかなければならないという立場から、国鉄闘争の重要な位置を見極めることが求められている」
「戦後革命期」―総評の結成
「戦後革命期、一九四五年の敗戦から一九五〇年の総評結成までですが、これは日本の歴史の中でも唯一革命的な情勢といえる時期ではないかと思います。ここで僕は、『戦後革命期』といったわけだけれど、こういう規定のしかたじたいが党派的なんですね。日本共産党の場合は、絶対そういうふうにはいわない。やはり六〇年安保闘争前後に、新左翼が登場して以来、この時期が戦後革命期だったんだ、その戦後革命に敗北して、今日の情勢もあるんだという認識が確立していったんですね」
敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令部)による占領政策のもとで、労働組合が雨後の竹の子のように誕生し、ナショナルセンターも結成される。ひとつは戦前の右翼的労働運動の流れをくむ総同盟であり、もうひとつは、日本共産党の指導下にあった産別会議である。
2・1に向かう闘いとその挫折
 この時期の象徴的闘いが1947年の2・1ストに至る闘いとその敗北である。官公労働者の経済要求、「飢餓突破賃金をよこせ」という闘いから、吉田内閣打倒の闘いへと発展する。しかしそれは、GHQのマッカーサーの指令で中止させられる。
この時期の象徴的闘いが1947年の2・1ストに至る闘いとその敗北である。官公労働者の経済要求、「飢餓突破賃金をよこせ」という闘いから、吉田内閣打倒の闘いへと発展する。しかしそれは、GHQのマッカーサーの指令で中止させられる。
「直前になって銃剣をつきつけられて、全官公の伊井議長が、NHKを通して有名な『一歩後退、二歩前進』ということをいって、ストの中止を指令します。これはやはり日本共産党の、『アメリカ占領軍=解放軍』という誤った規定の結果ですね」
「二・一ゼネストは挫折し、敗北しますが、なぜ敗北したのかははっき りしています。つまり党の問題だということですね。日本共産党は、正しく労働者階級の先頭にたつ前衛党ではなかったということです」
りしています。つまり党の問題だということですね。日本共産党は、正しく労働者階級の先頭にたつ前衛党ではなかったということです」
「一方、挫折したとはいえ、二・一ストにむかう日本の労働者階級の闘いの中に、アメリカ帝国主義も、復活をもくろむ日本帝国主義も、革命のヒドラを見たわけです。それで、これを徹底的に叩きつぶすという方向にカジを切ります。具体的にいうと、四七年の四月に日経連(日本経営者団体連盟)が発足します。そのスローガンは、『経営者よ正しく強かれ』でした」
その後、労働組合運動の分裂が始まり、産別民主化同盟や国鉄反共連盟ができる。他方、労働運動弾圧も強まり、1948年には政令201号により、官公労働者のスト権と団体交渉権が剥奪される。そうした中で定員法による国鉄10万人首切りが強行され、1950年の朝鮮戦争勃発を機にレッドパージの嵐が吹き荒れる。
 50年には、総評がGHQの肝いりで結成され、「北鮮軍の侵略反対、国連軍支持」を掲げる。だが、その総評は51年には「平和四原則」を決定する。「ニワトリからアヒルへ」の転換である。それを決定的にするのが国労新潟大会での「平和四原則派」の勝利である。
50年には、総評がGHQの肝いりで結成され、「北鮮軍の侵略反対、国連軍支持」を掲げる。だが、その総評は51年には「平和四原則」を決定する。「ニワトリからアヒルへ」の転換である。それを決定的にするのが国労新潟大会での「平和四原則派」の勝利である。
この51年5月に、動労の前身である機労(国鉄機関車労働組合)が、国労から分裂して結成される。当初は非常に職能意識の強い、右翼的体質の組合だった。
●【2】55年体制成立と60年安保・三池闘争
1955年が戦後体制の一つの画期をなす年となった。一つは自由党と民主党の保守合同で自由民主党ができ、左右に分裂していた社会党が合同したことである。さらに日本共産党が6全協を開き、それまでの山村工作隊や火焔瓶闘争を自己批判し、「議会を通じた革命」路線に転換した。
そして、この年に春闘が始まる。中野前委員長は次のように言っている。
「五五年には、二月に日本生産性本部の発足、これに対して総評は八単産共闘で春闘に踏み出すが、これは翌五六年から公労協も加わる本格的な春闘になります。……やはり日本は非常に低賃金です。そういう状況の中で、春闘がはじまる理由もあったし、積極的な面もあります。と同時に、労働運動が体制内に抱え込まれていく、つまり職場闘争の放棄、反合理化闘争の放棄につながっていく面をもっていました」
この時期、56年にソ連共産党第20回大会でのフルシチョフによるスターリン批判があり、ハンガリー革命に対するソ連軍による鎮圧が行われる。
国鉄新潟闘争と新左翼の誕生
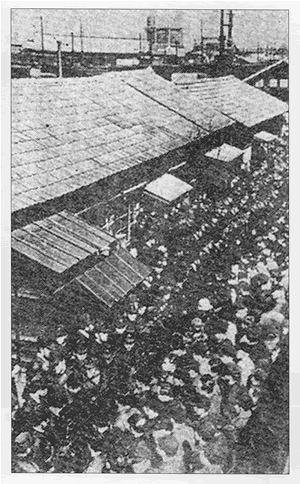 そして、57年国鉄新潟闘争が闘われる。57年春闘の激しい闘いに対して、国鉄当局が解雇などの大量処分を発令したことに対する処分反対闘争である。国労新潟地本は7月10から16日にかけて連日闘争をやる。
そして、57年国鉄新潟闘争が闘われる。57年春闘の激しい闘いに対して、国鉄当局が解雇などの大量処分を発令したことに対する処分反対闘争である。国労新潟地本は7月10から16日にかけて連日闘争をやる。
「新潟闘争というのは、戦後革命期を除く最も激しい実力闘争です。闘争の戦術だとか、公安との激突も辞さない闘いだとか、あらゆる意味で、戦後革命期を除くと最も激しい実力闘争です。そこには、五六春闘からはじまって五七春闘にいたる新たな全体的高揚、さらには……砂川基地反対闘争に代表される基地反対闘争の盛り上がり、こういうある種の戦闘的な雰囲気が、公労協の中、国労の中にも反映されて、新潟闘争が起こるということになります」
この闘争を指導したのは革同だったが、新左翼の出発に大きな影響を与える。
「新潟闘争のたいへんな感動の中で、国労や機労の青年労働者が日共から訣別し、新左翼に結集します。こうして日本の新左翼運動は、この時期、最も戦闘的な労働者と学生を結集して誕生するわけです」
 そして、「総資本対総労働」と言われた三池闘争が闘われる。59年12月、三井三池鉱業所は1492名の指名解雇を三池労組に通告する。単なる人員整理ではない。職場から「生産阻害者」を排除するということだった。会社側が全山ロックアウトに入ったのに対し、三池労組は無期限全面ストライキで対抗する。だが、第二組合の結成を許し、最後は60年8月に中労委が出した藤林斡旋案(指名解雇者はいったん復職して全員自主退職する)を炭労が受け入れ、闘いは収束される。
そして、「総資本対総労働」と言われた三池闘争が闘われる。59年12月、三井三池鉱業所は1492名の指名解雇を三池労組に通告する。単なる人員整理ではない。職場から「生産阻害者」を排除するということだった。会社側が全山ロックアウトに入ったのに対し、三池労組は無期限全面ストライキで対抗する。だが、第二組合の結成を許し、最後は60年8月に中労委が出した藤林斡旋案(指名解雇者はいったん復職して全員自主退職する)を炭労が受け入れ、闘いは収束される。
「この闘争を指導したのは向坂派だったということがある。向坂逸郎という人は労農派マルクス主義で、革命戦略は議会を通しての平和革命戦略だった。これが現実の賃労働と資本の激しい対立、総資本と国家権力の全力をあげた労働運動解体攻撃に対して対抗できなかった」
60年安保闘争は、52年にサンフランシスコ講和条約とセットで発効された日米安保条約の改定案が「極東条項」で日本が武力攻撃された場合、米軍は日本を守ることを義務づけることで、条約を「双務化」するものだった。これに対して、総評、社会党などが59年3月に安保改訂阻止国民会議を結成し、全学連を先頭に激しい闘いが展開される。国労、動労も6・4政治ストを打つ。
「六〇年安保闘争は、戦後革命期以来の最大の大衆的大闘争であったことは間違いありません。もうひとつは、五六年のハンガリー革命を期して誕生した日本における新左翼、反スターリン主義の運動が、全学連という形で公然と大衆的に登場したところにあります」
●【3】労働運動の右傾化とそれに抗する闘い
60年安保闘争以後、62年に同盟が結成され、64年にはIMF・JC(国際金属労連・日本協議会)が結成されるなど、労働運動全体の右傾化が進む。
「これは、反共主義、労使協調主義の立場から『民主的労働運動』を標榜するものですから、当然アンチ総評勢力です」「最大の問題は、総評がこれに対してまったく無視・軽視、あるいは黙認したということです。日本の労働運動の指導部というのは、概して右には弱くて、左はすぐ叩くという習性がありますね」
「だからIMF・JCの結成に対して、総評は何一つ対応していない。しかし実際はこのIMF・JC発足こそ、八九年の総評解散・連合結成の出発点だったわけです」
他方で、資本の合理化攻撃も激化する。反合理化闘争が本格的に問われる時代に入った。
三河島・鶴見事故と動労の安全闘争
「合理化の結果、国鉄では六二年五月の三河島事故(死者一六〇人)、六三年一一月の鶴見事故(死者一六一人)という大事故が相次ぎ、炭労では鶴見事故と同じ日に三井三池三川鉱における炭塵爆発事故で四五八人の炭鉱労働者が殺されるという大惨事が発生しました。三池が敗北したということは、職場支配権が会社側に奪われたということです。それまで三池の労働者は、危ないと思ったら炭鉱に入らなかった。『闘いなくして安全なし』という言葉は三池の労働者がつくった言葉です」
動労の中に、三河島事故を契機に安全闘争という思想がつくられ始める。
「そういう中で、一九五一年に結成された機労(機関車労働組合)が五九年に動力車労働組合と名前を変えました。動力の近代化や激しい合理化攻勢の中で、否応なしに闘う労働組合として脱皮せざるをえなくなってきていた。そこで決定的なのは、三河島事故、鶴見事故という二つの大きな事故です。これに対して労働組合の中でもどう対応するのかをめぐって激しい路線対立が起きました。やはり、闘うことを抜きにして安全を確保できないんだという勢力が勝って、それが後の動労の戦闘化、『鬼の動労』と言われるほどの主導勢力になっていきます」
「青森大会は三河島事故が起こった時の大会です。それまでは事故防止委員会を労資で設置していたんです。だけど労働組合と当局が話し合っても事故はなくなるはずがない。根本的には労働組合が要求を出して、団体交渉をして、それで闘う以外に事故対策は成り立たないんだということで、参加を拒否します。国労は参加していましたけれど、動労は拒否したので、当局との関係は一気に先鋭化しました」(『俺たちは鉄路に生きる2―――動労千の歴史と教訓』(2003年刊、以下『俺鉄2』と略)
「そして六三年一二月一三日、反合理化闘争をやりました。この闘いはすごかったですよ。尾久・田端が一緒にされるという基地統廃合に反対する闘争です。僕は千葉地本の青年部長になったばかりでしたけれど、尾久・田端の構内を警察機動隊が三〇〇〇人ぐらいで囲んでいて、僕たちは中に入れませんでした。そこで尾久駅から線路に飛び降りて、田端の構内まで入ったんですけれど、そうとう弾圧を受けて、警棒でぶん殴られれるという中で、大変な闘争をやりました」「こうした闘いを経て、初めて国鉄当局は、ATS(列車自動制御装置)をつけることを決めたんです」
「六四年の春闘に公労協が初めて、賃上げを要求する四・一七統一ストライキを提起しました。僕はこの時、品川機関区に動員で行ったことを今でも覚えています。特徴はいくつかあって、まず、公労協がストライキという言葉を初めて公然と使ったということです」 「この六四春闘でもうひとつ大きな問題は、日本共産党の四・八声明です。これは公然たるスト破り声明です。つまり『四・一七ストは、政府、資本、トロツキスト、修正主義者たちによる謀略であり、挑発である』というわけです」「ここには明白に、日共スターリン主義特有の労働者階級の自己解放闘争に対するものすごい蔑視と敵対があります。そういう体質が表面化したものとして、四・八声明はありました」(『軌跡』)
●【4】階級的労働組合への変革・飛躍
さて、動労千葉の歴史に話を移す。中野前委員長は、『俺鉄2』で動労千葉の「前史」として、「一九六三年は僕が当時の動労千葉地本青年部長に就任した年で、一九七三年は僕が動労千葉地本本部の専従の書記長に就任した年です」「つまり僕を中心とする動労千葉の青年労働者が、一〇年間の闘いを経て、当時の労働組合の権力を奪取したということです」と言っている。この時代は60年安保闘争以後の闘争の後退期から70年闘争の大高揚を経ていく過程だ。
「僕が青年労働者のころは、社会主義や共産主義というものがいったん色あせる状況の中で、『もう一回マルクス主義・レーニン主義を復権させよう』という動きが高まった。そして『社会党・共産党に代わる、もっとちゃんとした労働者の党をつくろう』という運動が非常に新鮮な光彩を放っていた。そういう壮大な事業の一角を、一介の労働者である自分が占めるんだという誇りとか、血湧き肉躍る感覚みたいなものがあった」(『俺鉄2』)
そういう中で、三河島事故を契機とした安全闘争、67年~69年の5万人反合闘争=機関助士廃止反対闘争などを激しく闘い抜いていく。
いまひとつは、65年に結成された反戦青年委員会の運動だ。これが全学連とともに、70年安保・沖縄闘争の大高揚を切り開く。中野前委員長は、千葉県反戦青年委員会の議長としてその先頭に立った。
「当時は、東京で毎日のようにデモがありました。総評のデモ、社会党系のデモ、反戦青年委員会の独自デモ、もう毎日のように動員、動員、動員の連続でしたね。みんな、東京でデモをやって、もちろん千葉でもやりますけれど、帰ってくるともう電車がないから職場に泊まって、それで翌日またデモに行くという繰り返しでした。デモに行って毎日機動隊とドンパチやるわけですから、青年労働者たちはおもしろくてしょうがない。どんどんデモの参加者が増えていく。おもしろいということは大事なんですよ」
「それで七〇年闘争の総括が重要なのですが、やはりわれわれにとって反戦青年委員会運動の総括が一番重要だと思います。ひとつは、もともとは総評・社会党の提唱ではじまった運動だけれど、実際は既成の党派とか、労働組合の枠や制動を突破して、七〇年安保・沖縄闘争の高揚を切り開いた。これは間違いなくそういえます。これが決定的です。六〇年以降日本の階級闘争に登場した新左翼が、独自の闘いを通して、あの高揚を切り開いたんだという自信と確信が、今日のわれわれにとって重要ではないかと思います」「二番目には、反戦青年員会というのは、歴史上かつてない戦闘的かつ大衆的な開かれた青年労働者、学生の共闘組織であったと自負しています。三番目にいえることは、反戦青年委員会運動が、労働運動の右傾化に抗して、街頭闘争に決起した青年労働者が職場に帰って、国鉄や全逓や東交などの反合闘争の高揚を切り開いたと言うことです。そして四番目に、それは民同労働運動からの脱却の萌芽をつくったのではないかということです」
「七〇年闘争の切り開いた主力は大半が二〇歳代です。僕は七〇年にちょうど三〇歳でした。これがあと一〇年たって、二〇歳の人間が三〇歳、三〇歳の人間が四〇歳になって、彼らがみんな労働運動を担うようになったら一体どうなるかのか。これはもう、社会党や共産党の時代ではないということです。これは帝国主義の側から見たらたいへんなこと、恐るべきことでしょう。こういう闘いを、あの七〇年を前後する過程で実現したんです。だからやはりこれに対する反動が当然強まる。その手先になったのが革マル派ということでしょう」「六〇年安保闘争のときは、社共を乗り越えたといっても、せいぜい学生に毛が生えたような組織でしょう。しかし七〇年安保・沖縄闘争というのは、このままいったら、社会党や共産党をのりこえる党ができるんではないかという現実性があった。われわれが感じたぐらいだから、国家権力だってこのまま放置できないと思っていたに違いない。だから権力は破防法も発動した。そして革マル派の襲撃がはじまるわけです」
「これは日本の階級闘争にとってたいへんなマイナスな事態だったかもわからないが、しかし避けて通れない問題でもあったのではないかと思います」「そして革マル派問題は、周知のようにこのあと今日にいたるまで、特に国鉄労働運動をめぐって最も深刻な、鋭角的な政治的・組織的攻防点になります」(『軌跡』)
滝口君の解雇撤回闘争
 さらには、生産性向上運動反対運動(マル生闘争)が闘われる。千葉では68年からだった。
さらには、生産性向上運動反対運動(マル生闘争)が闘われる。千葉では68年からだった。
「この背景には、国鉄労働運動の中に青年労働者を中心に大きな闘いの渦、戦闘的な雰囲気が出てきたということがあります。これに対して、当時の権力や国鉄当局は、反戦闘争と結合して国鉄闘争が爆発したら大変なことになると、大変な危機感を持ったわけです。……この時、新小岩支部青年部長だった滝口誠君が、三つの事件をデッチあげられて、懲戒免職処分を受けたわけです」
「この時に、労働組合としての動労千葉地本の姿勢が問われた。労働組合にとって、労働者が首を切られたことに対してどういう立場をとるのかは決定的なんですよ。それで動労千葉地本が、青年部だけでなく親組合も含めて二分したわけです。『滝口君を守れ』という勢力は青年部が中心でしたが、親組合の中にも『青年部の言うとおりだ。滝口に対する攻撃は明らかに活動家パージだ。こういうことを組合が容認したら、組合活動なんかやる人間がいなくなる。だからこれは絶対に守らなくちゃいけない』という人たちが出てきて、当時の千葉地本の大会や機関会議を二分したわけです」(『俺鉄2』)
これをめぐっては、裁判闘争を闘い、70年には勝利をかちとる。
他方で、動労内における革マルとの対立が先鋭になってくる。この滝口君の解雇撤回闘争に対して革マルが敵対してきた。
その過程では、69春闘の4・17バリケードストが闘われる。
「六九春闘で、四・一七第一波闘争の指令が出て、僕の所属していた千葉気動車区支部がストライキに入りました。この時、千葉気動車区の周りは機動隊に囲まれ、関東の鉄道公安官と職制が全部投入されて、ストライキをつぶそうという体制が敷かれました。そういう中で、全組合員が職場に籠城してスト終了時点まで闘ったんです」(同)
マル生闘争に勝利
そして、マル生闘争にも勝利する。
「どういうやり方かというと、まずマル生教育です。マル生というのは生産性向上運動の略です。日本生産性本部とタイアップして、現場の管理者を集めマル生教育をやります。真っ暗なところでキャンドルライトをつけて、泣くまで激論するとか、ともかく異様なことをやって、要するに洗脳する、人格を変えてしまうわけです」(『軌跡』)
「戦後初めて、労働者の側が生産性向上運動に勝ったんですね。民間の大手では全部やられてしまって、労働組合はだいたい右になっていく。国鉄は日本生産性本部に相談に行ってやり方をいろいろ教授してもらって、一気に始めるわけです。しかしそれに勝ったということですね」「なぜ勝ったのかと言うと、青年労働者の闘いですね。つまり七〇年安保・沖縄闘争、反戦青年委員会運動の中で年中デモに参加していた。そういう若い労働者が、このマル生攻撃粉砕闘争の先頭に立ったということです」(『俺鉄2』)
「当初は国労、動労もぐらぐら揺れていました。それで七一年八月に国労が函館大会を開くんですけれど、ここで当時の中川委員長が『ここまできたら座して死を待つより、立って闘おう』という、悲壮な演説をした。その当時まで国労は毎年毎年、ちょうど国鉄分割・民営化の時みたいに、国労から脱退者が出るわけですよ。鉄労がどんどん増えて、あっという間に一〇万人の組織になりましたからね」
「僕は当時、『東洋一の気動車の車庫』と言われた千葉気動車区の支部長をやっていましたけれど、これは大変でした。例えば二時間ぐらいのストライキだと、一〇人ぐらい運転士をマル生グループにとられちゃうと、汽車は動いちゃう。だからストライキをやっても、汽車は一本も止まらない。だけど実際上ストライキをやるから処分だけは来る。……この過程、七一年春闘の五・一八ストの時には、千葉気動車区以外の拠点指定の支部は全部ストを返上しちゃったんです。残ったのは最大拠点の千葉気動車区だけです。……結 局ストライキをやったんです。その結果、電車は一本も止まらなかった。だけど、やったことによって動労千葉はもったんですね」(同)
局ストライキをやったんです。その結果、電車は一本も止まらなかった。だけど、やったことによって動労千葉はもったんですね」(同)
「七〇年前後というのは、労働運動的には、一方で民間は全金など一部を除いて、全体を同盟・JC的勢力が制圧し、これが主導する右翼労戦統一の動きに官公労の一部である全逓や全電通まで引きずられるということがあり、他方では国鉄労働運動を先頭とする官公労働運動の巻き返しがあり、特に国鉄マル生闘争の勝利は、その後の右翼労戦統一の流れを一〇年遅らせたといわれるぐらい大きな位置を占めていたということがあります」(『軌跡』)
最先端を行った千葉の順法闘争
これに先だって動労千葉地本の青年部はさまざまな職場闘争を闘い、千葉地本を戦闘的に変革していく。例えば「大スコ闘争」だ。蒸気機関車に石炭をくべるのには小さなスコップを使うより、大きいスコップを使った方が仕事が楽になる。これを闘争にしていった。
「一番重要なことは、当時の機関助士、青年部で、この運動が猛烈に受けたということです。職場闘争は、現場の労働者に受けるということが大事ですよ」
「そういうことがだんだんできてくると、順法闘争を始めたわけです。ストライキ指令は下りないけれど、現場で働いているのは労働者ですから、労働者は仕事をよく知っているわけですよね。法規や規則、いろんな仕組みの弱点をついて、実際上列車を遅らせていくという闘いが順法闘争です」「千葉地本は動労の中でも順法闘争のあらゆる戦術をつくり上げたところです。検修ジグザグ行動と言って、交番検査というのがあるんですけれど、その検査の時に部品を全部はがしちゃって、付けない。それで四時半ごろになったら仕事をやめちゃう。そうすると気動車は部品が付いていないから、動けない」「やり始めておもしろくなると、労働者は知恵をいっぱい出します。これはもう心配しなくていい。労働者が一番よく知っているんです。そういう順法闘争も、千葉は動労の中で最先端でした。船橋市議をやっていた中江昌夫さんが当時、動労本部の組織部長をやっていて、彼がどんどん採用して全国化しました」(『俺鉄2』)
こうした職場闘争について、中野前委員長は重要な教訓を提起している。
「職場闘争というのは本質的に職場支配権をめぐる闘いだということです。職場支配権を組合側が獲得する闘争である。したがって非常に大変な党派闘争であるということです。党派闘争というのは、何か社会党と共産党が対立するとか、革マル派と中核派が対立するとか、そういうことだけじゃありません。……一番の党派闘争は、資本との闘争です。資本・当局が日常不断にまきちらす思想、イデオロギー、あり方、これとどう闘うかということが一番の党派闘争です」
 「職場闘争の核心は、資本に対する怒り、国鉄の場合は国鉄当局に対する怒りです。資本に対する怒りのない労働者に、職場闘争ができるはずがない。それから、こういう状況に追い込んでいる組合のダラ幹に対する怒りがなかったら職場闘争なんてできない」
「職場闘争の核心は、資本に対する怒り、国鉄の場合は国鉄当局に対する怒りです。資本に対する怒りのない労働者に、職場闘争ができるはずがない。それから、こういう状況に追い込んでいる組合のダラ幹に対する怒りがなかったら職場闘争なんてできない」
「これは敵の弱点を形成しているというところを見つけだすこと。僕らは運転職場ですから、運転職場で当局の最大の弱点は、安全ということなんですよ。つまり安全に列車を走らせるということは、何にも増して優先されなくちゃいけない。これは逆に弱点なわけです。敵のやってくることで安全を無視することがいっぱいある。これを逆手にとってやったのが、反合理化・運転保安闘争です」
「そして重要なことは、意識的・献身的活動家集団をいかにつくるかということです」
「だから職場闘争は、組合の指導部としての能力を形成する場であると言えます」(同)
●【5】反合・運転保安闘争路線の確立
船橋事故闘争に勝利
動労千葉の反合・運転保安闘争路線を確立したのが船橋事故闘争である。
「マル生闘争の渦中で起こったのが船橋事故闘争です。一九七二年三月二八日の朝七時に発生しました。つまりラッシュ時です。船橋駅の上りで、停車している電車に追突したという事故ですけれど、これで何百人という負傷者が出ました。当該運転士の高石正博君がただちにその場で逮捕されるという状況の中で、この事故に対してどう対応するのかが問われた」
「これは信号停電が原因です。総武線には停電になった時の補助電源があるんだけど、これがついていなかった。あとは二分間隔の過密ダイヤですから、ATSが作動しても、そのたびに止まっていたら電車が遅れてしょうがないから、『確認ボタンを押して消して、ゆっくり近づけ』という指導がされていた。そういういろんな要素を考えると、どう見ても乗務員の責任じゃない。明らかに国鉄当局の責任です。高石君が所属していた津田沼支部はできたてほやほやの支部で、全部青年部員です。僕は千葉気動車区の支部長でしたけど、これは一大闘争にしちゃおう、闘争にできるという感じを持って、ただちに千葉地本から本部に対して闘いの要求、つまり特認闘争を要求するということをやったわけです」
「その時に組合内でも大変な論争が起きました。つまり『事故問題は労働組合運動としては成り立たない』と言われたわけです。事故というのは大なり小なりそれだけとらえれば本人がミスしたということがある」
「そういう中で動労千葉だけは、『これは違う。反合理化闘争だ。反合理化・運転保安闘争だ』と。僕自身、激しく迫りくる合理化攻撃に対して、革マルみたいに『合理化絶対反対』と言っていればいいみたいな、こういうやり方ではとても通用しないと思っていました。やはり合理化反対闘争を具体的につくりあげなければいけない。その当時、この事故が起きたとたんに、ある意味では『これだ』と思ったところがある。それでこの船橋事故闘争を労働組合運動の最大の闘いにしよう、あらゆる努力でやり抜こうと決意するわけです」
その後、高石運転士は起訴され、千葉地裁包囲闘争などを闘い抜く。そして、76年には高石運転士の職場復帰をかちとる。
「動労千葉もそれまで、乗務員が中心の労働組合でありながら、事故問題には一切触れなかった。事故は手前持ちという感じだった。それをこの時、大胆に労働組合の課題として取り上げて闘争をやった。ストライキをやったり、順法闘争もやっているわけですから、処分も出ます。処分をかけて闘うということが、乗務員に組合への大変な信頼感をつくりあげたんですね。『ここまでやる労働組合こそ、本物の俺たちの組合だ』と」「後に動労千葉が分離・独立した時に、本部革マルとの関係で佐倉と銚子が一番厳しかったんですよ。しかし銚子のある年配の組合員が、『俺は千葉につく。船橋闘争みないなことをやる労働組合が本当の組合だ。動労本部は何をやっているんだ。ふざけんじゃない。俺は動労千葉と一緒にやる』と言って、彼の発言が決定的になって、全部本部に行きそうだったのが半分がこっちに来ました」
「この闘いをとおして反合・運転保安闘争路線の確立に成功し、このことが千葉が全国に比しても優位性を持ってそれ以降の闘いをやっていける基盤をつくったということですね。これは従来の国鉄の反合闘争の壁を打ち破って、機関助士廃止反対闘争という反合闘争の敗北をのりこえた地平をつくったと言えます」
「闘いなくして安全はないけれど、安全を確保するということは利潤を生まないから、必ず資本は設備、要員の切り捨てを進めます。どこでも合理化というのは必ず保安部門から始めます。そういうことをきちっと見据えて、合理化反対闘争を運転保安確立、つまり列車の安全を守るということと結合してやったことが、この成功につながったと思います」(同)
反合・運転保安闘争路線について、『甦る労働組合』(1995年刊)では「反合理化闘争の考え方」として、次のように言っている。
「合理化というのは今流に言うと『効率化』とか『リストラ』と言われる。本来、資本主義はそういうものだ。常によりコストの安い商品を作り上げる。そのためには労働者をどうやって効率よく働かせるかという、資本のひとつの自己運動だ。だから合理化は、労働者に対しては必ず労働強化と労働密度の強化という形で現れる。問題はそれに対する闘いだ」
「反合闘争は、資本制そのものに対する闘いのような要素がある。だから一労働組合が個別資本との間だけでそれを貫徹することは大変だけれど、しかし資本に譲歩を余儀なくさせるということはできる。その点、日本では総評時代から反合闘争は非常に中途半端だ」「動労千葉の場合は、国鉄の運転部門の労働組合であるという特殊性から、『反合理化・運転保安確立闘争』というひとつの路線を確立した。だから合理化反対ということと、安全に運転するということを結合させて、当局に立ち向かう路線をつくりあげた。これが動労千葉の第一のスローガンだった。それで約10年くらいは、ダイヤ改正のたびに労働条件を少しずつアップさせていくことを獲得してきた。僕が書記長の時だが、ダイヤ改正のたびごとに労働条件が良くなった」
スト権ストの総括
続いて75年には公労協のスト権ストが闘われる。75年10月26日から8日間という長期で大規模なストライキだった。
「このスト権ストライキをどう見るかということが、それ以降の闘いにとっても、あるいはわれわれがこれから闘いをやる上で非常に大事なことです。僕は民同労働運動の最後のあだ花だったと思っています。しかし、公労協傘下の多くの労働者が八日間にわたってストライキに立ち上がった。この意義を否定するものではまったくないし、問題はこのエネルギーを正しく指導しきれなかった指導部の問題だと思います」(『俺鉄路2』)
●【6】三里塚ジェット燃料貨車輸送阻止闘争
その 一方で、動労千葉は三里塚闘争と連帯し、ジェット燃料貨車輸送阻止闘争に立ち上がっていく。三里塚闘争は1966年の閣議決定に始まるが、地元の千葉県反戦青年委員会も当然にも取り組むことになる。
一方で、動労千葉は三里塚闘争と連帯し、ジェット燃料貨車輸送阻止闘争に立ち上がっていく。三里塚闘争は1966年の閣議決定に始まるが、地元の千葉県反戦青年委員会も当然にも取り組むことになる。
「反対同盟は、反対同盟の統制下にある限り、あらゆる支援を受け入れるということを内容とする三原則をつくったんです。それに基づいて〔六七年〕一一月三日、千葉県反戦青年委員会主催の集会に三派全学連が登場することになりました」(『俺鉄2』、以下、同)
そして、71年9月の第2次強制代執行阻止闘争など激しい闘いを反対同盟とともに闘い抜いていく。だが成田空港の一本の滑走路が完成し、開港が迫る。そこでジェット燃料の輸送問題が起きる。ジェット燃料を輸送するパイプラインが住民の反対で完成しないという中で、76年には、国鉄を使って千葉港と鹿島港から成田空港まで燃料を運ぶという計画が急浮上してきた。
「動労千葉は、『これと真っ向から闘いぬく』ということを確認したわけですが、当時はまだ動労千葉地本ですから、千葉地本として独自に指令を下ろして闘うというふうにはなりません。動労中央本部の決定に持ち込むということがないと闘いにならないという制約があった。七六年一二月一六日の中央委員会で、僕が中央委員に出て決議を提出して、それを満場一致で決定したんです」
「このジェット燃料闘争を闘うために、労働組合としての闘う論理をつくらなければいけない。そこで動労千葉としてはまず何よりも、今まで反対同盟を支援してきた立場から、三里塚空港には反対である。労農連帯―反対同盟の農民と連帯するという視点。それから危険なものは運ばないという運転保安の視点。労働強化を許さない。組織破壊を許さない。この四つの視点を確立して、この論理で三里塚ジェット闘争を闘おうと決定しました。僕は職場集会に行って、『労働組合はゼニ・カネのためだけに闘争をやるんじゃない。ゼニ・カネ以外だって闘争をやることはあるんだよ。そうだろう』と言ったら、みんな『そうだ』と言った。これでできたという要素があるけれど、僕はそういうことが非常に重要だったと今でも思っています」
 「これは福田内閣の最重要課題に対する闘いになるわけで、やはり大変だった。七七年一二月三日から闘争に入ります。最初の三日間は強力順法闘争ですけど、事実上、千葉だけの闘いになるんです。全国的な闘いになりません。動労本部は、非常にあやふやな安全確認行動とか、そういうたぐいのことしか指令を下ろさなかった。だけど、僕は書記長として、これを拡大解釈をして、めいっぱいやらせました。この三日間で三二二本の運休を出したんですね。それで首都圏はガタガタです」「その三日間の闘いを終えて、開港は三月三〇日ですから、それに向けてほぼ一〇〇日、闘争に次ぐ闘争の連続。もちろん順法闘争をやりっぱなしじゃありません。三日やってまたやって、また次やるというようなことを繰り返し、あるいはストライキをやったり、集会をやったりということで、阻止の声を上げました」
「これは福田内閣の最重要課題に対する闘いになるわけで、やはり大変だった。七七年一二月三日から闘争に入ります。最初の三日間は強力順法闘争ですけど、事実上、千葉だけの闘いになるんです。全国的な闘いになりません。動労本部は、非常にあやふやな安全確認行動とか、そういうたぐいのことしか指令を下ろさなかった。だけど、僕は書記長として、これを拡大解釈をして、めいっぱいやらせました。この三日間で三二二本の運休を出したんですね。それで首都圏はガタガタです」「その三日間の闘いを終えて、開港は三月三〇日ですから、それに向けてほぼ一〇〇日、闘争に次ぐ闘争の連続。もちろん順法闘争をやりっぱなしじゃありません。三日やってまたやって、また次やるというようなことを繰り返し、あるいはストライキをやったり、集会をやったりということで、阻止の声を上げました」
結局、この過程で当局は、助役にハンドルを握らせた。それも暫定的措置で、いずれ動労千葉の機関士に強制される。
「拒否から阻止へ」
「この状況を打開するためにはどうしたらいいかといろいろ考えて、七八年四月六日に千葉地本臨時大会を招集して、その中で『拒否から阻止へ』という方針を出したんです。つまり『燃料輸送を拒否する』ということじゃなくて、『ハンドルを握って自ら阻止する、われわれのストライキで阻止するという方針が、労働者としての真っ当なやり方だ」と」
「動労千葉は、この闘いをいろんな意味で教訓化しました。結局それ以降、春闘とかいろんな闘いのたびに、燃料輸送貨物列車をストライキに入れました。その集大成として八一年三月の闘争を構えます。成田空港は七八年五月に開港し、燃料輸送は三年間という期限が決められていたのに、三年間を超えてもパイプラインができないから延長すると提案してきました。『ふざけんな』と言って、八一年三月に指名ストから始まって全線を止める二四時間ストまで一週間にわたるストライキをやりました。これで当時の執行部四人が公労法解雇を受けました」
●【7】動労本部革マルからの分離・独立へ
「分離・独立闘争というのは、国鉄千葉動力車労働組合の結成にいたる過程のことです。それまで動労千葉は、国鉄動力車労働組合千葉地方本部という組織でしたが、七九年三月三〇日、国鉄千葉動力車労働組合という組織を旗揚げする」
動労革マルは、すでに触れた滝口誠君解雇撤回闘争や船橋事故闘争に対する敵対など、さまざまな敵対を始めていた。動労千葉地本青年部の6人に対して、73年1月、無期限の権利停止処分が出される。
73年に関川―中野体制を確立
「〔七三年〕9月に定期大会が行われ、この大会の中で関川委員長、中野書記長という体制が確立されます。僕は動労本部や革マルからは、いわば千葉地本青年部運動のリーダーと見られていましたから、そのリーダーが今度は親組合の専従書記長に就任した」「この時、僕が書記長に立候補したら、委員長にも、副委員長にも、誰も立候補しない。立候補届をだしているのは一人だけ。立候補すれば過激派たる中野洋、動労の中で最大のターゲットになっている中野と一緒に仕事をやるようになるわけだから、誰もやりたがらない。しかし、中野をたたきつぶそうと思っても、勝てる対立候補はいない。それで最後に関川宰さんが委員長を引き受けてくれて、大会流会の直前に三役体制が確立されました。それで関川・中野体制ができます。これによって、もう青年部問題ではなくて、千葉地本対動労本部、千葉地本対革マルという構造に転換したわけです」
動労津山大会での決定的裏切り
動労本部革マルがその裏切りを決定的にしたのが動労津山大会だった。
「七八年七月の津山大会で本部は、『三里塚反対同盟と一線を画す』と決定しました。『一線を画すとは何だ』と言ったら、『絶縁だ』と言いました。それから、『貨物安定宣言』を打ち出して、公然と反合理化闘争を放棄しました」「それとあわせて、『水本運動』と言って、水本という革マルの学生活動家が水死体で発見された事件を『権力の謀略だ』と言って、これを追及する運動を当時革マルが始めますが、その取り組みをこともあろうに動労の運動方針にしたわけです」「こういう無茶苦茶なことが起こったのが津山大会で、この時にはまだ本部方針に対して四〇%ぐらいの反対がありました。そして千葉地本が先頭に立って闘ったわけだけど、それが僅少差で負けた。その津山大会の四日目、大会が終了するころには、千葉地本の代議員が全員大会会場から排除されました。そして大会終了後に出口で待ちかまえていて、出てくる千葉地本の代議員と傍聴者に殴る、蹴るの暴行を働いたわけです」
この後、動労千葉は三里塚の全国集会の時に、「道路を一本隔てた第二公園」で独自集会を開き、「あとは組合動員じゃない。参加したい人間が参加しただけだ」という形式をとった。だが、動労本部は、関川委員長以下を査問委員会にかける。
「僕はこの問題が起きた時にいろいろ考えました。当時、千葉地本の各支部長クラスはもう腹を決めて、『動労本部と決別しよう』という意見が圧倒的多数です。これに対して『ちょっと待てよ』という人はほとんどいませんでした。一人で悩んで一番日和っていたのは書記長だった僕でした。それはそうなんですよね。独立したとして、財政は持つのか、当局との団体交渉権は成り立つのか、いろんな問題を考える。……僕は六畳一間にこもって一人で悩み苦しんだあげく、ある日執行委員会で、『ここまで来たら、腹を決めて、本部と決別しよう』と言いました。そう提起したらいろいろ意見が出ると思ったら、『おまえが腹を決めるのを待っていた』と言われました。『委員長以下俺たちは、みんな腹は決まっているんだ。書記長のおまえが腹を決めるのを待っていたんだ』と。執行委員会で、まったく何の議論もなかった。そこで決定して、そこから分離・独立へ向けて闘い始めたわけです」
「三月三〇日に動労本部が一〇四回中央委員会を開きました。そこで、関川委員長以下、僕も含めた四人の除名処分と執行部全員の組合員権停止処分を決定したんです。……われわれも同日に、動労千葉地本臨時大会を招集していたんです。それで動労本部が統制処分で関川委員長の除名を決定した直後、間髪を入れずに動労千葉の結成大会を開き、同じ役員を選出しました」
この後、79年4月17日の津田沼支部襲撃事件を始め、革マルの暴力的破壊攻撃が襲いかかった。だが、各支部の団結を固め、反撃し、これを打ち破る。
 この分離・独立闘争の勝利を総括して中野前委員長は次のように言っている。
この分離・独立闘争の勝利を総括して中野前委員長は次のように言っている。
「動労千葉の分離・独立闘争の勝利というのは、総評労働運動が始まって以来の事態なんです。つまり、組織問題が起きて、一四〇〇人の労働組合のうち一三五〇人が中央に楯突いた側について、多数を占めたというのは、初めてのことです。……闘う姿勢を堅持して闘って、それで九〇%以上の組織を獲得したという例は、総評労働運動史上初めてです。だから労働組合の運動を知っている人たちは、動労千葉の分離・独立闘争を、否応なしに評価せざるを得ないわけです」
「だからこの闘いをとおして、組合員が飛躍的に意識転換をかちとった。あるがままの労働者だったら、分離・独立した後、関川委員長のもとに来ませんよ。でもこの闘いをとおして、その後、八一年三月の三里塚ジェット闘争で五日間のストライキを闘った力も培われた。さらに国鉄分割・民営化に対して、国鉄の中で唯一、二波のストライキを敢行できた原動力も、七〇年代の一〇年間の革マルとの闘いにある。この中でいろいろなことを感じ取った、組合員の大変な意識変革にある、ととらえています」
●【8】国鉄分割・民営化反対闘争
次に、国鉄分割・民営化反対闘争について見ていく。
中曽根の「戦後政治の総決算」
「一九八二年一一月に首相に就任した中曽根康弘は、就任後初の記者会見で、『私は戦後を総決算する使命を担って総理になった』と公言しました。それ以降、『戦後政治の総決算』という言葉は、中曽根のメインスローガンになりました。一言で言って、憲法体制のもとにある日本の『戦後政治』を根本から転覆して、戦争のできる国家へと大改造しようということです」「そして中曽根は、『戦後政治の総決算』攻撃の頂点に臨調・行革攻撃をすえ、『(国鉄の分割・民営化は)中曽根行革の最大の目玉であり、行革の二〇三高地』と位置づけて、突っ込んできたのです」
この攻撃に対して、動労千葉は85~86年に2波のストライキに立つのだが、その直後の86年に刊行された『俺たちは鉄路に生きる――国鉄分割・民営化に異議あり!』(以下、『俺鉄1』)から、当時、中野前委員長が何を訴えいたのかを見ていく。
「国鉄労働者にとって、いまもっとも核心的なことは、みずからが血を流さずして外からの救いの手はさしのべられてこないし、ムードや同情だけでは問題は解決しないということです。このまま黙っていれば、国鉄労働者の全人格、全人生が破壊され、うやむやのうちに闇から闇へと葬り去られていくことは必至です。こんなことは許せない、いさぎよしとはしない、みずからの運命はみずからの手できりひらいていく、これが労働者の生きる道であるはずです」
「動労千葉は電車運転士や機関士、検修や構内の労働者の組合ですから、人一倍に運転保安問題に敏感なのです。十万人合理化とは、十万人の『余剰人員』をつくりだすための要員削減なのです。そこには、列車を安全に運行するための観点など、まるで念頭にありません。あらかじめの削減数があって、要員を切り詰めるという、恐るべき内容なのです。……『第二の日航ジャンボ事故』の危険性は、ほかならぬ現在の国鉄にあるのです」
「国鉄分割・民営化とは、これは国鉄の『再建』でも『改革』でも断じてない」「ならばいったい何か? まさに国鉄の労働組合をつぶし、国鉄労働者十万人の首を切り、国鉄にかぶせられた借金を国民に押しつけ、その上に国鉄という膨大な利権の温床にむらがって、これをズタズタに切り裂き略奪しあうことです。これが正体なのです」
“去るも地獄、残るも地獄”
「国鉄労働者にとっては、ひとりの例外もなく“去るも地獄、残るも地獄”がつきつけられているのです。まさに全事態ははっきりしました。われわれのとる道は、二つに一つしかありません。起ち上がってたたかい、敵の攻撃をうちくだいて生き残るか、屈服して奴隷となるのかです。これ以外に道はないのです」「動労千葉はどんなに血をながしてでもたたかう道を選んだのです。決断を下したのです」
「三人に一人の首が切られる。誰だって助かりたい。首になりたくないという気持ちがないわけではない。動労千葉といえども、よそとかわりない千百名の国鉄労働者の組合です」「われわれにしても、八七年四月一日まで何とかうまく泳ぎわたっていけたらいいなと、考えないわけではなかった。流血覚悟のたたかいをやらなくてもうまくいくのなら、それに越したことはないのです」「だけどどう考えても、これは何をやってもやられるな、ということがはっきりしたのです。どうあっても、どんなことをしても、しなくても敵はやってくる。絶対に逃げられないということなのです。絶対的にそうである以上、降りかかる火の粉はみずから払いのけるしかない。払いのけずには生きていけない。決然と起ってたたかうしかない、ということなのです」
「去年から三月までに全国で、国鉄労働者四十二名が自殺に追いこまれています。悔しくて胸がはり裂けてしまうような事実です。しかし、あえて言えば、このことの半分の責任は、国労中央の無責任な無指導・無方針にあることは明白であると思います」「それではどうすればよいのか? まさに、苦しい時は原点にかえれです。危機に直面している時ほど、原点にもどって原則的なたたかいをやることです。それこそが組合員を結束させて団結を強化し、多くの血を流すかもしれないけれども労働組合の骨格を残し、展望をひらく道であると確信できます」
“ストライキで元気になります”

「決戦方針を決断して提起すると、途端に全組合員はシャキッとなりました。組織全体がピーンと一本の筋でまとまったのです」「それ以降、組合員のたたかいへの気運や決意は、年配者も青年部員も、日一日とみるみる高まっていった。ストライキを打ち抜き、処分攻撃をうけてからは、この気迫、根性、戦闘性は全組合員のものとなった。そして、実に精力的、行動的、エネルギッシュになった。……動労千葉は、本当に“ストライキをやれば元気になります”そのものです」
「迷ったら原則に帰れ」
ストライキを闘い抜く決断をすることは並大抵のことではなかった。『俺鉄2』では次のように振り返っている。
「組合のリーダーであれば、国鉄分割・民営化攻撃が、政府、全資本、マスコミなどを含めて総がかりで襲いかかってきた攻撃であることは、十分わかるわけです。だから『じっと首をすくめておとなしくしていれば、嵐は通り過ぎる』というようなものではないことは強烈に自覚していました。国労と国鉄労働運動をこてんぱんにたたきつぶそうという攻撃であるとの認識は強く持っていました」「一方で動労千葉は当時一一〇〇人、国鉄労働者全体の中では本当に小さな勢力です。国家権力を相手に戦争して勝てるのか、それどころか残れるのか、本当に悩みました。しかも闘った結果、加わるであろう激しい弾圧を受けて、組織的にも財政的にももつのか、組合員がもつのか、あらゆることを考えました。労働組合側にとっていい条件は何もない。何よりも『鬼の動労』と呼ばれた動労が転向して敵の手先になったことは、労働組合にとって大変な出来事です。そして総評全体も力を喪失していく」「だから、悩みに悩んだと言っても、八二年に分割・民営化攻撃が始まってから約三年間、同じことがぐるぐる頭の中で回っている状態だったと言っても過言ではありません。……考えて考えて、悩んで悩んで、結局、『迷ったら原則に帰れ』という言葉どおり、『ここで組合員を信頼し、闘うことをとおして団結を固めていく以外に動労千葉の進む道はない』という結論に達したのが八五年前半ぐらいです。『やろうじゃないか。やる以上はとことんまでやろう』と腹を決めるわけです。本当に『死中に活を求める』決意でした」
「『よし、こいつらと生死をともにしよう。僕が本当に自分の全存在をかけて、命がけで闘いの先頭に立てば、必ずついてきてくれる』と確信を持ったし、『ここで一戦を交えよう』という決断になった」
「国労もストライキで闘おう」
そして、『俺鉄1』で、国鉄労働者全体への力強い呼びかけを行っている。
「勝利をかちとることのできる道は明確です」「国鉄労働者による全国での総反撃、そして国鉄労働者全体のゼネストをたたかいとることなのです。もっとはっきり言えば、国労がそのような反撃に起つことです。国労がストライキに起ってたたかうことなのです。敵にしても、この点を十分すぎるほど知っています。したがって、問題はそういう条件をどうやってつくりあげるかなのです。これが勝利の鍵をにぎる点なのです」「このために動労千葉は、身をもってストライキで起ったのです。犠牲をいとわず、みずから死中に活をもとめる道を選択したのです。その上でどうするのか? さしあたり、敵との対等の関係をたたかいとることです。敵とのやり合いの関係に入ることです。……これが当面の戦略目標です。……よくも悪くも世間が期待している以上、われわれ国鉄労働者の最大最強の武器で、すなわちストライキでたたかおうではありませんか」
「動労千葉第一波ストライキは、十一月二十八日正午から翌二十九日までの二十四時間ストライキとしてたたかいぬかれました。……いまでも、このたたかいを思い出すと胸に熱くこみあげるものがあります。国鉄労働者は魂のない、ふねけではなかったのです。やはり人間の熱い血がかよい心がかよった、戦後労働運動を牽引してきた中核部隊であったのです。このたたかいは満天下に証明してみせました」
「第二の目標は、国鉄労働者の総決起を切りひらくこと、その突破口となることでした」「この手応えはどうだったのか? それは何と言っても国労千葉組合員の決起であります。国労千葉の国鉄労働者は、動労千葉の首を覚悟したストライキ決起を前にして、国労中央のだしたスト破り方針に激しい反発を示しました。国鉄労働者としての魂が、彼らを奮いたたせたのです。……国労津田沼電車区分会では、もっと感動的なできごとが発生したのです。ここでは、乗務員組合員の大部分がスト破りはできないと強固に主張したのです。夜どおしの激論が繰り返されました。国労本部から派遣された渡辺中闘は、『当局の言うとおりに乗れ、拒否したら国労は面倒見ないぞ』というスト破り指令を繰り返すばかりでした。国労組合員はこの渡辺をとり囲んで、激しく食い下がりました。目に涙を浮かべて抗議しました」「この中で、ストライキ第一日目には、三名の国労組合員が渡辺中闘の面前に国労バッジをたたきつけて、乗務拒否に決起しました。……こうした中で、そのうちの二名が動労千葉に加入して、組織的に動労千葉組合員となってストライキに参加したのです。……こうした中で、十一月二十九日午前三時に、すっかり消耗し青ざめた渡辺中闘の口から『業務命令については本部あずかりとする』という新たな方針が発表されました。その瞬間、国労組合員は拍手と大歓声をあげて喜び合いました。この方針は、事実上スト破りの業務命令を拒否してともにストライキに決起するというものなのです。国労本部方針としてのストライキ連帯方針が発せられたわけです。現場の国労組合員の決意と突き上げが、国労本部からストライキでたたかう方針を引き出したのです」
「敵はたかだか千百名のストライキにたいして、われわれが考えている以上に革命のヒドラをみたのです。だから、あせっており、余裕がないのです。逆に言えば、われわれが、敵以上に必死にたたかいつづければ、勝利できるということなのです」
そして、86年2月には第2波のストに立つ。
「第二波闘争の核心的な目標とは次のことです。二十名も解雇された動労千葉が絶対につぶされないこと。まだたたかいつづけること。それどころか、ふたたびストライキに起ってたたかうこと。このことが何よりの核心点なのです」
「動労千葉は、労働運動史上かつてないようなたたかう労働運動をつくろうとしているのです。たたかえばたたかうほど、当然にも反動はおしよせてくる。労働者のたたかいの展望とは、この密集せる反動を打ち破って前進する中にのみあるのです。われわれは、そういう思想をもってたたかっている」
「動労千葉は、幾多の困難な問題を同志的・労働者的に解決しきって、第二波闘争をみごとにやりぬきました。それだけではありません。三十九日間にもおよぶ壮烈無比な激戦激闘を、元気にたたかいぬいたのです。動労千葉の真骨頂である団結をかためて、不屈の大エネルギーを爆発させたのです」
そして、『俺鉄1』は次の言葉で結ばれている。
「われわれ国鉄労働者には、いまや失うべきものは何もありません。失うものは鉄鎖のみです」「たとえ鬼といわれようと、蛇といわれようと、われわれは勝利のみをもとめて、たたかいつづけます」
なぜ闘うことができたのか
「動労千葉はなぜ闘うことができたのか」――『俺鉄2』では次のように言っている。
「動労千葉の闘いは何よりも一つ目に、戦後最大の労働運動解体攻撃に対して、唯一動労千葉が労働者の誇りをかけて闘い、一矢を報いたという意味を持っていました。全党派が存在する国鉄労働運動において、あらゆる勢力が敵の手先に転向するか、闘う方針を持たずに組織を切り崩されていくか、という状況だった。その中で、動労千葉が一矢を報いた。『ノー』と言える労働組合があること、『おまえらの言うことに唯々諾々と従うようなことはしない。屈服しないぞ』ということを示した。これが一番重要だと思っている」「二つ目には、国労が修善寺大会で『労使共同宣言』路線を拒否して、分割・民営化が強行された時点でも四万四〇〇〇人が残った。つまり動労千葉の闘いは、国労の旗が残るという事態をつくり出した大きな力となったと思う。そのことが結局、八九年には総評が解散して連合が結成されても、国労が連合に参加しないということをとおして、国労をつぶし、国鉄労働運動をつぶすという敵の狙いを阻んだと言えます」「三つ目に、国鉄分割・民営化が強行されてもなお動労千葉が残り、国労が残り、そしてそれ以降、『一〇四七名闘争』と言われる国鉄分割・民営化反対の闘いを、今も脈々と継続している。動労千葉の二波のストライキは、その基礎をなした闘いになったと思います」
重要なのは、「労働組合観の違い」だ。
「動労革マルや国労民同・革同とわれわれとでは、まずやはり、労働組合観が全然違った。労働組合運動に対する認識が全然違ったということです」「当たり前のことではあるけれど、労働組合とは幹部のものではなく組合員のものです。労働組合は、資本・当局のあらゆる攻撃に対して組合員の階級的利益を守るために、団結して闘いぬくものです」
「僕は書記長の時から『民同労働運動を乗り越えるというのはどういうことか』と考えていました。それは根底的には、動労千葉に結集している労働者の階級性、本来労働者が持っている力を掛け値なしに全面的に信頼し、それに依拠して闘うということです。それ以外に労働者は生きようがないから、口だけじゃなくて、掛け値なしにそうしてきました」「だから僕は、自分のナマの姿をさらけ出して労働者と話をするし、付き合う。そうでないと組合員は信頼してくれません。『あいつは口ではうまいことを言っているけど、本音は違う』というんじゃダメなんです。だけど、僕は組合員にべたべたしないで、必要な時は叱りとばしますけれどね」
さらに「時代認識の違い」があった。
「当時、分割・民営化攻撃をいったいどうとらえるのかという背景には、明らかにこの時代をどう見るのかという時代認識の問題がありました」
「動労革マルは『冬の時代』論で、『冬の時代に闘うなんて、労働者階級の戦いに敵対する行為だ』という理論まで組み立てる」「国労は『これだけ攻撃が激しく厳しい時代だから、たこつぼに入るしかない』という認識でした。典型は日共・革同です。日共・革同は、戦後革命期に壊滅的な攻撃を受けたという恐怖感を今も引きずっている。だから国鉄分割・民営化のような攻撃が出てくると、敏感に察して、『これに立ち向かったら、戦後のレッドパージや日共の非合法化のような攻撃にまたさらされる』という恐怖感を持って、闘いを放棄していく」
「動労千葉はどういう時代認識を持っていたのか。あの当時も、僕は組合員によく『支配階級の側が盤石な時には、労働者がどんなに闘っても敵はびくともしない。しかし危機の時代には、われわれの闘いによって敵を揺るがすこともできる。労働者階級の側から見れば、チャンスの時代なんだ』と言っていた」「分割・民営化攻撃というかつてなく激しい攻撃の中にも、敵の矛盾点があることを見てとれるかどうかということだと思います」
「結局、分割・民営化攻撃の中ではっきりしたことは、日本の左翼はほとんどすべてが体制内左翼だったということです。国労には、日本の左翼の全党派が存在していて、それぞれがそれなりに闘うことによって、国労はかなりの戦闘性を持っていた。しかし結局は体制内労働運動に過ぎなかった。だから、分割・民営化という戦後最反動の攻撃に対して、転向して敵の手先になるか、闘わずして屈服するかという道を選んだわけです」
「そういう意味では、体制内労働運動とは違って、マルクス主義的な物の見方をすることができたということが、動労千葉が唯一闘いぬくことができた核心だと言えると思います。……僕はよく、『物取り闘争になっちゃったらダメだ』と言ってきました。改良主義的改良闘争はやらない。『だけど、物も取るよ』と、革命的改良闘争はやる。そういうふうに闘ったからこそ、労働条件という面でも、国鉄の中では最高の労働条件を千葉がかちとったんです」
戦後労働運動の「神話」を打ち砕く
さらに、「『闘えば必ず分裂する』神話を打ち砕く」ことだ。
「僕は、動労千葉が分割・民営化に反対してストライキで闘うことだけをとらえてほしくない。ストライキを闘い、公労法解雇と清算事業団送りを含めて四〇人も首を切られて、にもかかわらずそれ以降一六年間も闘いを継続しているということを認識してもらいたい」
「『闘えば必ず分裂する』というのが戦後労働運動の『神話』でした。この『神話』を分割・民営化闘争をとおして動労千葉は完全に打ち砕いたと、自信を持って言えますよ」「もうひとつ、戦後の労働運動の歴史の中で、『右の側』からの組織拡大はいくらでもありますが、『左の側から』の組織拡大を実現することができた労働組合というのは、いまだかつて存在しないんです。動労千葉はそれにも今、挑戦中です。JR総連を解体して、平成採の青年労働者を一気に組織してやろうという組織拡大闘争です」
それは今、6人の平成採の獲得を始めとする組織拡大として実現されている。
さらに、なぜ分割・民営化に反対して闘いぬけたのかについて、革マルへの怒りが闘いのバネになったこと、現場の活動家集団の存在、職場闘争・実力闘争が闘いの土台にあったことなどを挙げている。
そして、動労千葉の総括と教訓として4点を挙げている。
「1.『二者択一』の場合は、左を選択することが正しい―原則を守るということ」「2.労働者は闘うことによってのみ団結を堅持し、展望を切り開くことができる」「3.指導部・活動家が団結して闘いの先頭に立てば、組合員の八割以上は必ずついてくる」「4.一〇四七名闘争は、国鉄分割・民営化反対闘争の延長戦である」
●【9】JR体制下での闘いと1047名闘争
分割・民営化以後、1988年に、中野前委員長は、『対談集 敵よりも一日ながく――総評解散と国鉄労働運動』を共著として出版している。その中で、鎌倉孝夫埼玉大学教授(当時)との対談、佐藤芳夫東京地域連帯労働組合委員長(当時)との対談を行っている。
鎌倉さんとの対談では次のように言っている。
「国労というのが、そうやって分割・民営化を前に、結局一戦も交えることなくずるずると後退していった、にもかかわらずいまなお四万の労働者を組織しているというのはたいへんなことですよ。僕はいつもいっているんだけれど、歴史的にみても戦後の労働運動破壊をめぐる攻防の中でも例を見ない、非常に特殊な状況ですね。まあ動労千葉がストライキをやって、分裂もせずにそっくりそのまま残っているというのもいままでにないことだと思うけれど、国労が分割・民営化攻撃に対してなにひとつ中央指導部の方針が出せない中で、なおかつ四万人残ったというのも例がない。……ここには、やはり戦後労働運動を牽引してきた国鉄労働者の階級性とか戦闘性の片鱗が示されていると僕は思うんですね。そしてここがあるから、分割・民営化の矛盾がいま大きく暴露されはじめているし、またここに連合の発足という形で進行している労働運動全体の右傾化に対する対抗基軸があることは間違いないと思うんですね」
「ポイントは、これは労戦統一という名の分裂工作、解体工作なんだから、これを打ち破るというのは組み合わせではないんですよ。やはり大衆的な闘いをつくりあげることが問われている。なにか幹部があっちこっちであれこれしゃべって、それで粉砕できるんだったらこんな簡単なことはない。逆にいえば、やっぱり大衆的な運動を展開できなかったら、連合を揺さぶることも、粉砕することもできない。その意味で、僕は国鉄をめぐる攻防にひとつの可能性を見出しているということですよね。国労は四万になったとはいえ全国的にあるわけですから。……だから、僕は、いまだ終わっていない国鉄分割・民営化をめぐる攻防が依然として一番重要だと思うんですね」
また、1989年に共に全国労働組合交流センターを結成することになる佐藤さんとの対談では次のように言っている。
「僕ら六〇年安保の世代だから、佐藤さんより一〇年ぐらい後から労働運動を始めていますけれど、動労千葉なんかでも、民同労働運動をどう克服してゆくのか、あるいは自分の中にもある内なる民同的体質をどう脱却してゆくのかを、職場のいろいろな闘いの中で絶えず考え、追求してきましたよね。そういう僕の経験からいうと、やっぱり労働組合には譲れない原則があって、そこは絶対曲げないということが重要ですよ。もちろん生きた労働運動だからいろんな妥協や譲歩は当然ある。しかし曲げられない原則というのはやはりあって、そこはどんなことがあっても死守するということが一番大事じゃないか」
「たとえば動力車労働組合の場合、合理化攻撃というのは、単に労働強化というだけではなくて、事故という問題に必然的に結びつくわけですね。事故が起これば、一番先頭に乗っている乗務員労働者は死の危険にさらされるわけだし、同時に多くの乗客をたいへんな危険にさらす。だから動労の場合、合理化反対ということは同時に運転保安に結びつくという特殊性があった。その中で僕らは運転保安闘争というものをつくりあげていくわけです。これはもちろんいろんな産別の、いろんな単産が、それぞれの特殊性にあった運動をつくりあげてゆくべきなんだけれど、われわれの場合はそれが反合・運転保安闘争だったわけです」
民同労働運動の問題点
「なぜ日本の労働運動がこうなったか、佐藤さんのいったことを別の角度からいうと、要するに民同労働運動の問題ということだと思うんです。その場合、権力との関係の問題が非常に大きいんではないか。いま全民労連とは何かを考える場合一番重要なのは、帝国主義の危機の時代だからこそこういうものが出てきたということだと思うんです。だから連合は単なる労使協調ではない。民同的な労働運動の考え方では、資本の分けまえをできるだけ労働者が多くとる、そのためには一定の闘争をかまえるという話にもなるし、いや合理化に協力してパイを大きくするべきだという主張にもなる。そこで左右の対立が出てくるけれど、全民労連はそんな水準じゃない。体制の危機を背景にもっと積極的に資本と国家権力の意志を担ってゆく運動ですね。これは国鉄分割・民営化過程での動労革マルの主張なんかに鮮明に現れた」
「民同労働運動の最大の問題点というのは、その出発点から一貫して、権力問題に非常に弱いということですね。GHQのレッドパージへの屈服がその出発点ですよ。労働者の闘いというのは、賃上げ闘争であれ反合闘争であれ、究極のところ国家権力とぶつからざるをえない。ところが民同はそこを見据えないで、なんとか権力の許容する範囲内で動こうとする、そういう運動だったんじゃないですか」
「だからやっぱり、今の状況を突破する道がどこにあるかといわれれば、僕は躊躇することなく国鉄戦線をめぐる攻防にあるというんです。これだけの攻撃を受けながら国労が四万残った。動労千葉も頑張っている。これが敵を震え上がらせているわけですよ。……もちろん佐藤さんがいわれた少数派組合で頑張っている人たち、地域で頑張っている人たち、争議団で頑張っている人たち、みんな重要で、いろいろな闘いを全部糾合していかなくちゃなんないんだけれど、その主軸になるのはやっぱり清算事業団五〇〇〇人を先頭とする四万の国鉄労働者ですよね。共産党や協会派がどんなに右往左往したって、この四万はいわば日本の労働運動の精鋭ですよ。しかも清算事業団の問題なんか解決の見通しもない。いわば発火点でしょ。ここで火がつけば、全民労連傘下の労働者だってみんな痛めつけられて、腹を立てていない労働者いないんだから、どう動くかわからない。国鉄労働運動を主軸にして、再び日本の労働運動をつくり直してゆく、その大きな可能性がここにあると思うんですね」
連合に抗する対抗基軸が国鉄闘争
そして、総評が解散し、1989年に連合が結成される。この右翼労戦統一に対する対抗基軸が国鉄闘争なのだと中野前委員長は鋭く提起し、新たな闘いを開始する。特に清算事業団闘争が1047名闘争として発展するのに、動労千葉の闘いが果たした役割は大きかった。
「国労という総評労働運動の最有力単産が、総評がなくなって一四年間も連合に加わらず存在し続けているのは、一にも二にも、一九八七年四月時点で七千数百人がJR不採用になり、さらに九〇年四月時点で一〇四七人が国鉄清算事業団から解雇され、これに対する『解雇撤回・地元JR復帰』の闘いが続いてきたことにあります。国労本部はこれに対して、労働委員会闘争以外にこれといった指導をしてこなかった。いや当初から一日も早く国鉄闘争を終わらせたいという姿勢を露骨に示していたんです。しかし国労闘争団や動労千葉争議団、全動労争議団の不屈の闘いがこれを許さなかった。そしてこの闘いは、国労組合員だけでなく、連合傘下で呻吟する多くの労働者の共感と結集を組織しました。『この仲間たちを見捨ててよいのか』という広範な労働者の意識が連合内外に沸き上がり、それに支えられて一〇四七名の一六年間の闘いという、文字どおり史上最大・最長の争議団闘争が、国鉄分割・民営化を強行した国家権力と真っ向から対決するものとして今日まで継続してきたのです。ここにこそ、まさに連合に対する鋭い対抗基軸があったわけです」(『俺鉄2』)
動労千葉はJR体制下で、88年5月に、千葉駅や亀戸駅、銚子駅などで次々とストに立ち、89年12月5日、JR移行後初めて本線乗務員をストライキに入れた。
「前年の八八年一二月に、中央線の東中野駅で追突事故が起こり、動労千葉の組合員ではありませんけれど運転士が死に、乗客もしんたんです。……ちょうど一年後の一二月に、『東中野事故一周年・運転保安確立』を掲げてストに立ち、三五〇本の列車を運休に追い込みました」「動労千葉が運転保安闘争としてストに立ったことは、多くのJR労働者に共感を持って受け止められて、この闘争は大成功しました」(同)
90年3月ストから1047名闘争へ
そして、動労千葉の闘いが1047名闘争を生み出す。
「九〇年四月の清算事業団労働者の首切りを目前にした三月一八日、動労千葉は『労働委員会の命令を守れ。動労千葉一二人の採用差別者をJRに復帰させろ。解雇は絶対に許さない』と八四時間のストライキを構えました。当初は国労にあわせて一九日から二一日の七二時間ストを予定していたんですが、本部役員を職場に入れなかったり、津田沼支部では組合事務所の周りをトタンで囲い込んだり、いろいろなスト妨害がやられて、『正当な労働組合の争議行為に対する明らかな介入だ』と抗議して、一二時間前倒しでストライキに突入しました」
 「半日前の一八日正午からストライキに入ったから、東京圏、東京―千葉が完全にガタガタになっちゃった。総武快速線もガタガタ、東京まで全部止まりました」
「半日前の一八日正午からストライキに入ったから、東京圏、東京―千葉が完全にガタガタになっちゃった。総武快速線もガタガタ、東京まで全部止まりました」
「結果としては、この闘争が全国を席巻して、当時の国労本部や社会党、その他諸々の画策を全部吹き飛ばしたわけです。そのことにより、九〇年四月一日、国鉄清算事業団が一〇四七人の労働者を整理解雇して、一〇四七名闘争が始まったという、大きな意義を持った闘いになりました。動労千葉の威力を示し、国労闘争団の中にも動労千葉を見直すという動きがこのころから広がり始めます」(同)
清算事業団闘争は労働運動の精華
そういう中で、岩井章元総評事務局長との共著『大失業時代の労働運動』を1994年に出版する。
「結論的に言うと、僕は清算事業団闘争は、国鉄労働組合、あるいは戦後の国鉄労働運動が現時点の中で作りだした、精華だと思っているわけです。財産だと思っているわけですね。この財産をもってもう一回出直していく、もう一回国労を軸にして連合に抗する労働運動を作り出していくという立場に立ったならば、僕は相当な影響と現実性を持った運動体としてできるのではないかと思う」
「もうひとつ僕は、執拗に主張していることがあります。動労千葉の場合には、むしろ解雇された労働者、うちの場合には清算事業団十二人を含めて、公労法解雇二十八人ですから、計四十人が解雇されているわけです。だから動労千葉は、『解雇撤回・清算事業団闘争勝利』というふうに言っています」「動労千葉の場合には、むしろ本隊の労働者が、JRに残っている労働者が『この解雇された人たちは自分たちの先頭に立ってたたかって、それで解雇された、だから俺たちの今があるんだ』という意識が強いわけですよ。ですから、すべてのたたかいをまず本隊の労働者が先行する。清算事業団闘争についてもです」「国労の場合は、清算事業団の千人に近い労働者が、本当に涙ぐましいたたかいを展開している。本隊の労働者は必ずしもそれと一体になっていないという、ここが今度の(中労委)命令の問題なども含めて主体的に総括する場合には、考えていかなければならないのではないか」「ですから、本隊の労働者に対しても、同じように分割・民営化攻撃というか、苛酷な合理化攻撃、権利剥奪の攻撃がどんどん続いている。それと清算事業団の苦闘を結合すると、もっと違った局面が生まれてくるのでないかということです」
「だから、僕たちの責任は非常に重いのではないかと思っていて、僕は『国鉄闘争水路論』を提唱しているんです。国鉄闘争水路論、つまり国鉄闘争というのは戦略的な課題であり、だからひとり国鉄労働者の問題ではなくて、広く全労働者の共通の課題だから、国労や動労千葉がおかしなことをやったらどんどん批判すべきである」「あるいは、ここに戦略的に結集するという形を通して、ひとつの大きな水路にして、それで連合を下から攻めあげるという方法にしていかないと、これから来るであろう大失業の時代、大変な時代が目前に迫っているわけですから、日本の労働者はがたがたになってしまう」
「確かに総評時代も、反合闘争をしっかりやれていたかというと、必ずしもそうではないということはありますよ。しかし、今の連合というのは、資本になりかわって労働者にそれを強制することを行っていますね。例えば希望退職など、全部組合がそれを認めてしまうということね」「だが、これからの大不況下の状況では、こういうやり方では説明がつかないことが、連合にも突きつけられていますよ。今まで『三種の神器』と言われていた終身雇用制、年功序列型賃金、それから企業内労働組合という日本型の雇用制度が、音をたてて崩壊する過程に入ったのです。しかも重要なことは、資本の側から積極的に言い出してきていることだと思うんですね」
マルクス主義の復権を
「こういう状況の中で、具体的にどうするのかという点が問題です。前にも話しましたが、僕はやはり総評労働運動というのはマルクス主義であり、社会主義を作っていこうとしたというのが結論です。いわば労働運動というのは資本主義、帝国主義を打倒するということが、運動の核心でなければならないと」 「だから僕はマルクス主義をどう復権させていくのかが、これからの運動のひとつの大きな基本になると思う。そこをどういうふうにするのかを抜きにして、連合に抗する労働運動というのは、成り立たないと思っているんですね。連合の弱点はそこだと。本来はマルクスが言ったとおりに、労働現場では労働者が首を切られ、徹底的に痛めつけられているにもかかわらず、それを否定するという労働運動というのは、本質的に成り立たない」「だから僕は、そこをはっきりさせていく必要があるのではないかと思っている。そう考えれば考えるほど、清算事業団闘争を中心とする国鉄のたたかいというのが、ある意味ではポスト連合下の日本の労働者のたたかいを、労働者の現状を打開する唯一の存在ではないかと僕は思っている」
そして中野前委員長は、本書の「あとがき」で次のように言っている。
「あいつらと俺たちは違う」
「この対談中、私には岩井さんの国鉄闘争を何としても勝たせたいという思いが痛いほどひしひしと伝わってきた。国鉄闘争を何としても勝たせたいという点では、若輩の私も決して人伍に落ちないつもりである」「年齢や運動経歴で十六、七年も違う私が、こうしてともかく、岩井さんと長時間の対話をすることができたのも、ある重要な一点で共通項を有していたからだと痛感する。その一点とは、岩井さんが対談の中で、イギリスの労働運動にふれて、『階級的労働運動などという教育はなかったにもかかわらず、あいつら(資本家階級)と俺たち(労働者階級)とは違うという感覚・立場が明確だった』と指摘している点である」「まさしく『あいつらと俺たちとは違う』のである。岩井さんは今日までずっとこの感覚を持ち続けてこられたからこそ『国会議員』になろうなどと右こ左べんすることなく、労働運動一筋に生きてこられた。……私も、動労千葉の組合員も、『高邁』な教育は受けていなくても、皆この感覚は強烈である。だからこそ、国鉄分割・民営化のあの熾烈な攻撃にも耐え、分割・民営化後の理不尽きわまりない不当な差別、選別攻撃をはね返してきたのだ。国労闘争団の諸君も同じだと思う」
和解路線では勝てない
そして、中野前委員長は、1047名闘争の勝利に向かって、国労の「和解路線」を批判し続け、JRとの闘いを訴えた。
「動労千葉は一貫して『国労闘争団は、国鉄労働運動が生み出した精華だ』という立場から、国労内のこのような傾向〔『闘争団はお荷物だ』と称して、一〇四七名闘争の切り捨てを主張するグループが登場する〕に強く反対してきました。僕は動労千葉こそ、国労の誰よりも国労闘争団の闘いを評価してきたと自負しています」(『俺鉄2』)
「国労は一貫して政治解決路線、つまり和解路線です。膝を屈して『どんなことでも飲むから、少しでも返してくれ』という運動です。動労千葉は違います。JRに復帰を求めているんだから、JRと闘う。しかもJRの中心会社はJR東日本なんだから、『JR東日本の中で闘って力関係をひっくり返さない限り、JR復帰など成り立たない』という立場で、JR体制との闘いを軸に据えた一〇四七名闘争を闘ってきました。だから労働委員会や裁判だけに依拠した闘いじゃありません」
「なぜ、戦後日本労働運動の重戦車と言われた国労が、分割・民営化攻撃に対して一戦も交えられなかったのか。このことについて国労本部は総括していません。国労を指導している協会派や革同・日共も総括していません。総括していないから、今も同じことをやっているわけです」
「1047名闘争は、中労委での和解が破産し、98年5月28日には東京地裁が「JRに責任なし」の反動判決を出し、2000年には「JRに法的責任なし」などの4党合意を執行部が受け入れるが、7・1臨大では国労闘争団を先頭にして演壇占拠で大会を流会に追い込む。その後、2001年になって4党合意受諾を大会決定するが、結局破産する。
「四党合意が破産した後、四党合意反対派も、ある意味で茫然自失状態になってしまいます。彼らもやはり政治解決路線だからです。もちろん労働運動ですから政治解決も和解もあります。しかしそれは、組合が団結を強化して闘って、資本や政府が困った時に初めて出てくるものです。それを最初から方針化したら、際限なく屈服する以外にありません。それを国労は典型的にやった。国労以外の労働者は、こういうあり方を他山の石にしなければいけない。『こういうことをやったら本当に惨めになる』という典型です」
中野前委員長は、最後の著書となった『新版 甦る労働組合』(2008年刊)でも、警鐘を鳴らしていた。
「1047名闘争は、日本労働運動以上に例のない大量首切りをめぐる長期争議であり、国労闘争団をはじめとする1047名の解雇者は、労働者の誇りをかけて不屈に闘ってきた『日本労働運動の宝』とも言うべき存在である。それが、スズメの涙のカネで『解決』=屈辱的屈服をしてしまっていいのか。断じて否だ」
「仮に『和解』で決着したとして、国労はどうなるのか、どの道を選択しようとしているのか。解雇撤回を投げ捨てることは、国鉄分割・民営化に賛成することであり、国労を解散し、JR連合に吸収・合併されることにならざるを得ない。あるいは、JR資本ともJR総連革マルとも闘わないことになる。このように『和解路線』は、国鉄―JR労働運動の反動的な再編に棹さすものになることは疑いない」
今日、国労などの4者・4団体が受け入れを表明している「政治解決案」とは、まさにそのようなものである。中野前委員長は、心底から怒っているに違いない。
●【10】労働組合の革命的意義を復権
労働者学習センターを設立
中野前委員長は、2001年10月に委員長を勇退し、常任顧問となるが、その直前の4月には労働者学習センターを設立し、労働学校を開設する。
ところで、その前に中野前委員長は、98年の5・28反動判決を機に、それまで進めていた「闘う労働運動の新たな潮流」運動を、全日本建設運輸労働組合関西地区生コン支部、全国金属機械労働組合港合同、動労千葉の3労組共闘による「たたかう労働組合の全国ネットワークをつくろう」という毎年の11月労働者集会に発展させてきた。
この闘いは日米韓の3カ国連帯の集会に発展した。さらに労働学校などをとおして青年労働者の育成に力を注ぐ。動労千葉を常任顧問として引き続き指導し続け、後進の指導に全力を注いだ。
それは2006年に胆管癌が発見され、闘病に入る中でも続けられた。その中で、自身の労働組合論とマルクス主義の復権の闘いに全力を挙げた。その集大成が、1995年出版の『甦る労働組合』を全面改訂した『新版 甦る労働組合』として結実した。
多くの青年労働者・学生が本書に触発され、闘いに決起している。発行された08年はリーマン・ショックを契機とした世界大恐慌の始まりの年であった。
「起きている事態の本質は何か。『資本主義の終わり』が始まったということだ。ブルジョアジー(資本家階級)が従来のあり方ではプロレタリアート(労働者階級)を支配できなくなり、統治能力を失ったということだ」「“古い支配の方法がすでに崩壊し、新しい方法は確立されていない。誰もが現状の変革を望んでいる。労働者階級が自発的に行動を開始している”――このような情勢を革命情勢と言う。これはロシア革命を指導したレーニンのことばだ。現在は、まさにそのような情勢の始まりだ。ブルジョアジーが統治できないのなら、『労働者に権力をよこせ!」ということだ」
時代認識をきちんと持つこと
そして、「時代認識をきちんと持つこと――四つのキーワード」を提起している。
「キーワード1 帝国主義(資本主義)体制は、労働者を食わせられなくなった」
「資本主義とは、労働者の労働力を商品として、それを徹底的に搾取して利潤を上げる社会だ」「しかもこの労働力という商品は、こき使えば使うほど能力を発揮する」「労働力商品を搾取することによって利潤を得る、このことなくして成り立たないのが資本主義だ」「資本家は、一部の連中だけが金儲けしながら、労働者に対しては労働力商品として自己を再生産していけるという、資本主義がひとつの社会として成り立っていける最低の構造も全部ぶっ壊してきている」
「キーワード2 帝国主義(資本主義)体制は、戦争する以外に延命できない」
「アメリカがその象徴だ。01年に起きたアメリカでの同時多発ゲリラに対して『対テロ』という名でアフガニスタンへの侵略戦争を開始し、03年にはイラクへの侵略戦争を開始した。今、この二つの戦争がいずれも泥沼化している」「いまや、世界中に戦争の火種がくすぶっている。アメリカは次にはイラン、北朝鮮への侵略戦争を狙っている」
「キーワード3 帝国主義(資本主義)体制は、歴史的命脈が尽き、社会の発展の桎梏となった」
「戦後60年余り、帝国主義ブルジョアジーが必死で先延ばしをはかってきた世界大恐慌がいよいよ現実のものとなろうとしている。われわれが経験したことのない事態だ。1930年代の世界大恐慌と同じ、いやそれをも上回る帝国主義の基本矛盾の爆発がこれから現実のものになっていくのだ」「核心は、現代の資本主義は命脈が尽きて、社会の発展にとって桎梏になったということだ」
「キーワード4 全世界で労働者の反乱が燎原の火のような勢いで始まった」
「まさに、世界でストライキが嵐のように巻き起こっている。重要なことは、これらの闘いが、どこでも大幅賃上げを掲げ、体制内労働運動の制動をのりこえ、分岐・流動をつくりだしながら闘われていることだ」
そして、次のように訴えている。
「僕は、世の中で一番感動する闘いをやってきた経験者は動労千葉の組合員だと思っている。ストライキを何度も仕組んで、『ストライキは素晴らしい』と、涙を流して感激しながら指導してきた経験を持っているのは、僕ら動労千葉の指導部ぐらいだと思う」「労働者が立ち上がって敵に立ち向かうこと、一人の労働者として生きるための闘いに立ち上がることを経験するには、ストライキを闘えなければダメだ。デモにしても、何万人という労働者が学生と一体となって東京で大変なデモを展開するとなったら、みんな感動する。感動すると、次はもっとやろうというふうになる。今、運動に一番欠けているのは、感動だ。僕は、革命運動というのは人間の、労働者のあらゆる行為の中で最も感動的な、ロマンに満ちあふれた営為だと思っている」
「青年労働者の中から、労働運動の担い手が登場したこと自身が重要なことだ。これまでの日本の労働運動は、60年代や70年代に労働運動を始めた人間が支えてきた。しかしそれ以降、組合運動らしい組合運動をまったくやっていないから、その後のリーダーが育っていない。それが今、帝国主義の本格的な危機の時代に、新しい世代の労働運動のリーダーが登場してきた。これはとても大きなことだ」
「労働者が人間らしく幸せに暮らすためには、階級対立をなくして自らが支配者になる以外にない。つまり革命を起こす以外にない。資本主義体制はそのままで、労働条件の改善を積み重ねていったら労働者は幸せになれる、なんてことは絶対にない。これが階級的労働運動の根本的な考え方だ」
「考えてみれば、資本主義社会においては、圧倒的多数は労働者階級であり、労働者を支配している資本家階級は圧倒的少数者だ。にもかかわらず、なぜ資本家階級の支配が成り立ってきたのか。労働者の階級的利害を本当に貫く者が主流派にならなければ、労働者の勝利はないのだ。ここが勝負の時だ。労働組合を甦らせること、この一点に労働者階級の未来がかかっている」
11月労働者集会が日米韓の国際連帯に発展していることについては、「『万国の労働者、団結せよ!』のスローガンが本物になる時が来た。インターナショナルな組織がなければ、世界革命は実現できない。いよいよ、世界の革命情勢と切り結ぶ闘いをつくりださなければならないと強く思っている」と言い、さらなる国際連帯の発展を追求してきた。
労働組合とは闘うための組織
そして、「労働組合が時代の最前線に登場する時が来た」として、「労働組合とは何のためにあるのか。それは闘うための組織だ。つまり労働者が資本と闘うために労働組合は必要である」と指摘している。
「マルクスは『共産党宣言』の中で、『ブルジョアジー(資本家階級)はなによりも、自分たち自身の墓掘り人を生み出す。ブルジョアジーの没落とプロレタリアート(労働者階級)の勝利は、いずれも不可避である』と言っているけれど、そのとおりだ。本質的に労働者階級と資本家階級は非和解的な存在である。しかしその非和解的存在である労働者階級に広範に依拠しない限り、資本主義それ自身が成り立たないという、極めて矛盾した関係にあるわけだ。だから、あらゆる手段を使って労働者の団結形態を解体することに一切の精力を傾けてきたのだ」
「労働者の団結形態が、なぜ労働組合という形をとるのか。労働者はなぜ労働組合をつくるのか。労働組合がなくては、資本から徹底的にこき使われて、低賃金と労働強化で権利もまったく認められない。人間としてまったく扱われない状況に置かれる。それに対する怒りから労働組合はできるわけだ。だから、必然的にその組織は権力をつくらなければいけない。つまり指導部をつくらなければいけない。そして資本に対して要求を突きつけて、団体交渉から始まっていろんな闘争を行ない、自分たちの要求を資本に強制する。そういう権能を持っている。だから労働組合なのである」
「俺たちが代わってやる」
「『労働者をこんな低賃金でこき使っておいて、結局食わしていけないようだったらもうお前ら辞めろ』ということが大切だ。そして『労働者を食わしていけないのはお前らのやり方が悪いんだから、俺たちが代わってやる』という考え方を対置すべきだと思っている。つまりこれほど過酷で、食ってすらいけないような賃労働を強制する資本から自らを解放するためには、資本制を廃止し、労働者がとって代わるということだ。それは基本的な考え方としてそうあるべきだということだけではなくて、それで労働者は団結できるということだ」
「社会主義とはそういうことだ。資本主義がつくりだした膨大な生産力に依拠しない限り、社会主義にもならない。そしてなぜ社会主義がいいのかと言えば、それは労働者階級が主人公で主導権を握っている社会を指すからだ。あり余るほどの膨大な生産力がない限り平等や公平も実現しない。つまり社会主義は資本主義がつくりだした膨大な生産力に依拠する。その生産を担い、握っているのは労働者階級だ。労働者階級が唯一、資本主義を打倒し、社会主義を建設できる能力を持っているということだ」
 「労働組合と党は限りなく一体」
「労働組合と党は限りなく一体」
労働者階級の党のあり方についても重要な提起を行っている。
「労働組合の中には、政党を毛嫌いする勢力もいる。しかしそもそも、労働組合運動をめぐる一番の党派闘争は、資本との闘争だ。資本・当局が日常的にまき散らす思想、あり方とどう闘うのかということだ。そして、このことをめぐって労働者の中にさまざまな考え方が生まれる。これが党派闘争となって闘われる。だから、労働者内部での党派闘争は、労働運動の前進にとって大きな意味を持つ」「もちろん僕は、労働組合を党派に従属させたり、政党を労働組合の上に置く考え方には反対だ」
「『労働組合と党は別』ということをやたらと強調する諸君もいる。その典型が、『区別と連関』論を掲げつつ『区別』ばかりを強調してきた革マルだが、共産党を含めて、あらゆる党派に大なり小なり共通したことだ。しかし僕は、その区別ばかりを主張する考え方には反対だ。いやむしろ、『労働組合と党は、限りなく一体であるべきだ』と考えている」「『党派の主張を労働組合に持ち込むことに反対』と言う人もいる。しかし、ある政党に属する労働者が、自らの主張を労働組合の中にストレートに提起するのは当たり前のことだ。党の中で話していることと組合の中で話すことを分けることの方がおかしい。問題は、労働者に理解されるように訴えているのかどうか、ということではないのか。その主張が正しいかどうかを判断するのは労働者だ。労働者の支持を得られるように大いに提起すればいいし、労働者と大いに議論すればいい。そして、労働者は自らの力で、労働者に徹底して依拠した労働者党をつくりださなければならないのだ」
●【11】義理・人情と路線・思想が必要だ
「青年労働者こそ主役だ」という章では。マルクス主義の核心を実に端的に語っている。
「正しい路線と思想というのは何か。一つは、今われわれが生きている社会が資本主義社会であることをはっきりさせることだ。資本主義社会において、労働者階級と資本家階級の間の階級対立は非和解的だ。そしてすべては力関係によって決まる。そういう考え方をしっかり持つということだ」
マルクス主義者になるべきだ
「さらに重要なのは、労働者が社会の主人公であることに誇りを持つことだ。つまり、労働者がこの世の中をすべて動かしている。そうであるからこそ、労働者が団結した時に、労働者階級は社会を変革する力を持つのである」「そして、労働者に国境はないということだ。マルクスの『共産党宣言』の結語は『万国の労働者、団結せよ!』だ」
「これらはすべて、マルクス主義の思想である。マルクスだけが、労働者の存在を認めてくれた。マルクスだけが、この世の中を動かしているのは労働者だと言った。マルクスだけが、世の中を変革する力を持っているのは労働者階級だけだと言った。そうである以上、労働者はすべからくマルクス主義者になるべきだ、と僕は言っている」
 組合員がわかった時に正しい方針に
組合員がわかった時に正しい方針に
続けて、「義理と人情が必要」と説いている。
「それから僕はいつも、『労働組合には理屈だけでなく、義理・人情が必要だ』と言う。思想や闘う路線がないとダメ、というのはもちろんだ。しかしそれだけでは労働者は団結しない。思想や路線と『義理・人情』、人間関係と言ってもいい。この二つが一緒になった時に、初めて労働者は団結する」「人間関係がないところで、いくら立派な路線を提起しても、組合員は『うん』とは言わない。『正しい方針』というのは、組合員がわかってくれた時に初めて正しいものとなることを忘れてはいけない。『組合員が納得しないような方針は、間違っているんだ』というぐらいに思っていい。正しい方針であれば、必ず労働者はわかってくれる。組合員が『そうだ』と思って、それを実践して闘った時に、初めて正しい方針になる」
「だから動労千葉は、非常に『義理・人情』に厚い労働組合である。だけど、『義理・人情』だけが強調されても困る。やはり労働組合は、思想、路線が大切である。その両方をきちんと持たなければならない」
労働組合運動を「天職」に
そして、青年労働者に訴えている。「核心は、労働組合運動を『天から授かった天職だ』と思って、自分の人生をかけるということだ。人生をかけなかったら、労働者はついてこない」「そしてそうやって腹を固めると、労働運動ほどおもしろい運動はない。本当に真剣に考えて、討論して、方針を決めたら、そのもとに組合員は動いてくれる。労働運動ほど素晴らしいものはない」
「労働組合は、やりようによってはこれほどおもしろいものはない。どれほど人間を鍛えるかわからない。人間の持っている素晴らしさを、どんどん発揮させるのが労働組合だ」「その核心は、青年労働者が握っている。労働運動に本当に活力を与えるのは、青年労働者が労働運動に結集し参画することだ。やはり歴史の主人公は労働者だし、とりわけ青年労働者だから」
労働者に徹底的に依拠し信頼する
「僕は、動労千葉を結成した時から猛烈に言っていた。日本の労働運動の悪しき神話、つまり『闘えば分裂する』という神話を絶対に打ち壊さなければならないと。労働組合というのは、いざという時に力を発揮する存在でなければならない。もちろん労働組合だから敵の攻撃を全部はね返すことはできない。しかし、悩みや苦しみやどんなことでも相談にのれる、話し合える仲間がたくさんいる。そこで団結ができる。お互いに助け合える。こういうものに労働組合をしていかなくてはいけないと思ってきた。そして『労働者である彼らに徹底的に依拠して、絶対に信頼する』ことを実践してきた」
「一人ひとりの労働者の持っているエネルギー、労働者性に基礎を置く。これがマルクス主義の神髄だ。それがなければプロレタリア革命は成り立たない。……マルクス主義というのは、労働者階級を獲得し解放する思想だ。だから労働者の持っているエネルギー、力の素晴らしさや、一人の人間が本気になった時にどれだけ強い力を発揮するか。こうしたことが、いわばマルクス主義の根底にある。ここがあるから革命が可能になるわけだ。革命は、労働者一人ひとりのものすごい飛躍を生み出す」「動労千葉の分割・民営化の時の闘い、労働者の姿。僕は『あれこそが革命の現実性だ』と言っている」
さらに労働組合の意義を明確にする。
 「階級的労働運動というのは、資本家階級と労働者階級がいて、非和解的な階級対立があることをはっきりさせて、その階級対立をなくすことをめざす労働運動だ。こういうことをはっきりさせているのが、マルクス主義なのだ」「そして、労働組合は労働者階級が団結する手段だ。さらに労働組合というのは、階級対立を伴う旧来の社会全体の転覆の準備の手段である。つまり階級対立をなくすための社会転覆の準備をするところだ。労働組合とはそういうものなのだ。労働組合運動の中で、労働者階級は、自分たちが権力を握った時の能力を身につけるわけだ」
「階級的労働運動というのは、資本家階級と労働者階級がいて、非和解的な階級対立があることをはっきりさせて、その階級対立をなくすことをめざす労働運動だ。こういうことをはっきりさせているのが、マルクス主義なのだ」「そして、労働組合は労働者階級が団結する手段だ。さらに労働組合というのは、階級対立を伴う旧来の社会全体の転覆の準備の手段である。つまり階級対立をなくすための社会転覆の準備をするところだ。労働組合とはそういうものなのだ。労働組合運動の中で、労働者階級は、自分たちが権力を握った時の能力を身につけるわけだ」
「要するに、階級的労働運動ということは『労働者階級と資本家階級、つまり労働者と資本家との関係は非和解的なんだ。だから結局、労働者自らが資本家階級の権力を打倒し、権力を奪取して労働者階級の社会を建設しない限り、労働者は幸せになれない』という考え方だ。レーニンは『労働組合は革命の学校である』と言ったけれど、労働運動も革命運動の一翼だ、という位置づけだ」
「つまり労働運動も革命運動の一翼であり、その革命は労働運動を軸にして成り立つということだ。階級に基礎を置かない階級闘争はないからだ」
「労働者が自分の能力に目覚め、『俺だってこういうことができるんだ』という自覚ができた時に、その運動は進む。そういう労働者を無数に排出する以外に階級的労働運動は成り立たないし、革命も実現しない。そういう労働者が無数に生み出された時に、革命は成就するものだと思う」
最後に、中野前委員長が「はじめに」で記した次の言葉で、本稿を締めくくりたい。
労働者を軽んじ、蔑視する考えに取り込まれない限り労働者は必ず勝てる
「僕は、労働者を軽んじ、蔑視する考えに取り込まれない限り労働者は必ず勝てると確信している。難しくはない。団結して立ち上がれば道は切り開かれる。侵略戦争を阻む力もそこにある。そのために、自分たちの労働組合を甦らせ、労働運動の現状を変革することだ。それこそが今、最先端の変革である。闘うことはけっこう楽しいものだ。朗らかに闘おう」
この思想は、動労千葉と全国・全世界の闘う労働者階級の中に生き続けるだろう。









