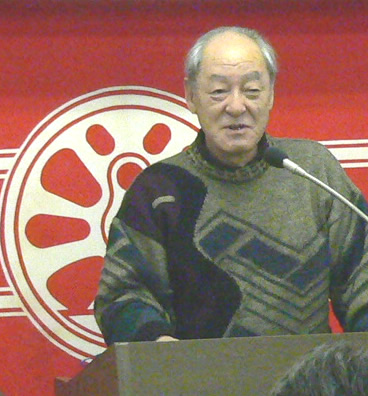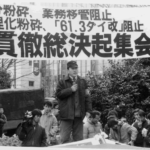動労千葉の闘う路線とは、
 「動労千葉は義理と人情で、仲間意識が強い」、こういうことがよく言われています。勝浦運転区廃止の時に、当局側は「風土が悪い」と言ったんです。 「タテの線じゃなくてヨコの線が強すぎる。仲間の意識が強すぎて、職場を中心として指揮命令系統が貫徹できない。風土が悪いから、勝浦運転区は廃止するしかない」と、こう言った。 私はそれを聞いて相手も敵ながら見るところをちゃんと見ているなと思った。確かに動労千葉の組合員は仲間意識が強いんです。
「動労千葉は義理と人情で、仲間意識が強い」、こういうことがよく言われています。勝浦運転区廃止の時に、当局側は「風土が悪い」と言ったんです。 「タテの線じゃなくてヨコの線が強すぎる。仲間の意識が強すぎて、職場を中心として指揮命令系統が貫徹できない。風土が悪いから、勝浦運転区は廃止するしかない」と、こう言った。 私はそれを聞いて相手も敵ながら見るところをちゃんと見ているなと思った。確かに動労千葉の組合員は仲間意識が強いんです。
だけど、私はそれは一面だと言いたい。動労千葉の本当の強さは、路線の正義性です。私はもっとそのことに 組合員が自信を持ってほしい。ずっと動労千葉の闘いを見ていて、路線にブレがない。きちんとした路線を組み立てて、そこに組合が団結して闘っている。中野前委員長は、以前からよく言っていました。人は理論だけじゃ動かないだけど理論がないと運動にならない 私は全く同感です。
路線を生み出していく過程が大事
路線の正義性と言うと、≪あらかじめ正しい路線があって、それに皆が目覚めてやればいい≫という印象になるけれど、そうじゃない。正しい路線を作っていく過程が大事なんだよね。労働者がその時代と真っ正面から向き合って、大衆的な英知の中で、実践と経験を通じて理論化して方向性を作っていく。そしてみんながそれに習熟していく。たゆみない闘いの連続の中から路線を生み出していくということなんだよ。
それは、あまり格好の良いことじゃないんですよ。初めに、首尾一貫した路線があって、それに向かって「さぁ組合員、みんなのこの指とまれ」と指令するような運動じゃない。 動労千葉の運動は模索の歴史ですよ。今だから「間違っていなかった」という意味で「路線が正しかった」と言えるけど、ずっとみんなで一緒に模索しながらやってきた。現実にぶつかって、じゃあ組合としてどう対応するか、みんなで知恵を出し合って、議論して実践してきた。その積み重ねの中から作り出してきたものなのです。
船橋事故にしても、「これは労働者の責任じゃない」と言い切って闘うという立場が、あらかじめ組合の中に作られていた訳じゃない。あの当時は、みんな「しょうがない」「事故は自分持ち」という意識が当たり前だったんだから。
それに対して「そうじゃないんだよ」と組合員の即自的な意識からすれば極めて飛躍した、だけど本質に根ざした視点をポンと定義できる人間がいた。 この存在は大きいね。それは、社会の本質をきちんと捉えているから提起できたことなんだよね。それで、ポンと提起したら、その主張が組合員の心を本当につかんで、大衆運動として広がっていった。
いろいろ激論もしました。中野前委員長を中心にして、布施、吉岡、西森、山口、そういう我々の世代と一緒に侃々諤々、支部の役員も交えて議論をしました。だけど、そこで「こうだ」と決めた時には、みんな一緒に結集して闘ってきた。それが動労千葉の闘いの歴史だと思うんですよ。
ですから義理と人情だけじゃない。路線です。その路線を確立のために、組合員が討論に参加して、皆で自分たちの行動決めていく。誰かの指令や誰かの思いつきじゃない。そういう運動を展開してきた。その歴史が、今も連綿として引き継がれていると思います。
◆指導部の責任 徹底的に考え抜く 本質を見る
これからの運動で一番心に留めておいていただきたいのは、動労千葉の指導部を担う人たちの責任の問題です。これは十分に自覚してほしい。
やっぱり動労千葉闘いの歴史を振り返ってみると、中野前委員長の卓越した指導力が決定的だった。それなしに烏合の衆でみんなが言いたい放題討論して言ったって、こんな闘いはやってこれなかった。
彼の良いところは、何よりも自分の頭で考えること。しかも徹底的に考え抜く。表面的なものや現象にとらわれずに、常に本質を見ようとする。「こういう社会現象の本質はどこにあるのか」と。物事の背景を見抜く。国鉄当局の攻撃だって、敵がどのような意図を持ってこういう攻撃に来たのかということを徹底的に分析する。
◆上から命令しない しゃべり役と聞き役
それから中野前委員長は上から命令しなかった。
しゃべり役と聞き役。しゃべり役というのは皆に状況をお知らせる。「こうだよ、ああだよ、こうなるよ」。それで後は組合員が何を言うのかをよく聞いている。そしていろんな議論を聞いて、みんなが考えていることを路線的にまとめあげて、その中で執行委員会としての方針をきちんと出す。そういう能力はものすごい。だからみんな、中野君が「こうしよう」と言うと、納得しちゃうんですよ。これはなかなか難しいことなんだよ。
私たちは、中野君が何か突発的な方針を出したという記憶はないんだよね。
彼は書記長であり、執行委員長であったから、彼が「こうしよう」と方針を出せばそれでまとまるかもしれない。だけど、彼が「これで行こう」と言った時には、執行委員のあらかたが「そうだよな」と思うような状況が煮詰まっている。だから、全く奇異に感じない。それだけの理論と実践の積み重ねを通して、それをきちっと理論的にまとめ上げて、現実の状況を反映した方針を提示するのが彼だった。だから組合員が「えぇ?」と意表をつかれるような反応するようなことは全くなかった。
◆「組合員が何を考え、どう受け止めているのか」
我々が一番腐心したのは、「組合員が何を考えているのか」ということです。組合員が、起きている事柄をどう受け止めているのか。
そのためには前提として、まずその事柄を組合員に公開しなければいけない。きちんと伝えるということです。今どういう状況なのか。敵の攻撃がどんな攻撃なのか。他労組はどう対応しているのか。そして、われわれが抵抗しなかったら一体どういう事態が生まれるのか。そういうことを組合に知らせ、組合員と一緒に議論をして、組合員に十分理解してもらって、そして「万機公論に決すべし」です。きちんとした路線を提起して、そこに向かって全部一気に団結して闘いを展開する。
組合員が闘争の中で鍛えられ成長していくのと、きちんと歩調を合わせて、指導部が組合員と一緒に学んで、きちんとした路線を確立していきたいということなんです。
ですから、これからもいろんな局面が来ると思いますけれども、上から方針を提起するんじゃなくて、事実を組合員に知らせる。組合員と一緒になって議論をする。そして最終的に路線をきちんと確立したら、全員で行動する。こういう動労千葉の気風をずっと継承していって欲しいと思います。
◆「正しい運動」なんてどこにもない
今の時代に国鉄分割・民営化反対闘争について、「同じようにやれ」「動労千葉の闘いは素晴らしい」とか言ってもダメ。目の前にある状況を自分たちでちゃんととらえて、自分たちの頭で考えて、自分たちの運動を作っていくのが大事なんだよ。運動というのは、その時の時代の時代と、そこに生きている人がつくっていくもの。あらかじめ出来上がったお手本なんかない。闘いの精神を教訓化することは重要にしてもね。
いま自分たちがいる場所で、敵はどういう攻撃をかけてきているのか。自分たちはどう対応していくのかを真剣に考える。我々がかつてやったように、模索に次ぐ模索だろうけれど。その時代に生きる人たちが主体的に作り出していく運動以外に、「正しい運動」なんてどこにもありません。