
03春闘 パンフ No.1
 |
|
03春闘 パンフ No.1 |
|
◆03春闘 パンフ No.1 |
|
■ ■ ■ |
目次
| |
|
1 安全の基本をくつがえす。 |
1 国土交通省令の抜本改悪 |
|
1 信号に対する考え方の大転換、無線万能主義 |
1 千葉支社の再回答 |
|
1 異様の会社賛美! |
Ⅵ 闘いなくして安全なし! --- 原点にかえり、反合・運転保安闘争の強化を 1 進行の指示運転の即時中止を |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ① 素材・仕様・規格を詳細に指定する基準から必要最低限の性能基準へ移行する。 ② 社会的規制については、行政の政策目的に沿った必要最小限のものとする。 ⑨ 事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 市場原理に委ねられるべきものは市場原理に委ね、国の関与を縮小するとともに、行政手法についても事前規制を合理化し事後チェックを充実する。 鉄道事業者の自主性、主体的判断を尊重できるものとする。(運輸技術審議会答申) |
要するに、全てを市場原理に委ね、規制は必要最小限にし、こと細かな決めごとはしない。概ねかくかくしかじかの性能をそなえていればよい、後は鉄道会社の自由な判断・裁量にまかせるということだ。しかも、事前規制はやめて事後チェック型に転換する、つまり事故が起きたら後で考えればよいというのである。
こうした考えのもとに、運輸省令の条文はごく簡素なものにされ、以前の省令に定められていたあらかたの内容は、「解釈基準」という名称で、それ自体改悪されたうえで、強制力を一切もたない付属資料のような扱いにされてしまったのである。
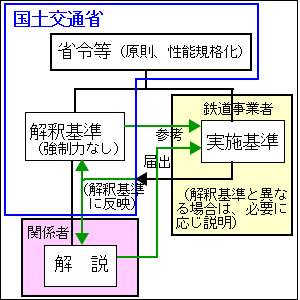
ここには恐るべき発想の逆転がある。そもそも安全は、市場原理に委ねたりしたら間違いなく崩壊するからこそ、これまで国土交通省令(以前の運輸省令)で、企業に詳細な規制をかけてきたのではなかったのか。
市場原理とは、利潤を生み、競争に勝つためにどれだけコストを抑えるのかという原理だ。一方安全の確保」という課題は膨大な人的投資・物的投資を必要とするものであり、それ自体は利潤を生みださない。市場原理と安全は相反する水と油の関係にある。それを市場原理一辺倒の発想に転換しようというのだ。
JRは、国土交通省令が変わったのだからJRでも運転取扱いに関する規程を変えるのは当たり前のことで、何も非難されるいわれはない、という対応をとっている。だが実はその主張自体ペテンというべきものだ。
省令の具体的な改訂作業は、部門ごとに「調査研究会」が設置されて行なわれたが、そのメンバーは、運輸省や学識経験者とともに、鉄道事業者や鉄道総合研究所が加わっており、議論の実質的な主導権をとったのはJRであり、JRの意向がつよく反映されたかたちで運輸省令の改訂が行なわれたのである。つまり「自作自演」の改悪なのだ。
国土交通省令の規制緩和-抜本的改悪は、ニューフロンティア21やニューチャレンジ21など、第二の分割・民営化攻撃と表裏一体のものだ。
この大リストラ計画の大きな柱をなすのは、車両検修・構内運転、保線・電力・信号通信、駅、車掌など、鉄道事業の中心的な業務を全面的に外注化=アウトソーシングしてしまうという攻撃だ。その底流に流れる発想は、弱肉強食の論理-市場原理の徹底した強調であり、ただひたすらコスト縮減と利益率の最大化のみを追求するという思想である。
とくに「進行の指示運転」の背景には駅業務の大合理化がある。この間も営業関係では、地方の小駅を中心に無人駅化や駅そのものの委託化が進められてきたが、ニューフロンティア21では、こうした攻撃がこれまでのレベルをこえて一挙にエスカレートされようとしている。
すでに千葉支社でも「駅体制の見直し」と称して、22駅の駅長を廃止するという提案が行なわれており、来年度以降派遣社員への置き換えなど駅業務の全面的な外注化攻撃が開始されようとしている。
言うまでもなく、代用手信号を出したり、列車を誘導したりという運転取扱いを派遣社員に行なわせることはできない。要するに「場内信号機に対する進行の指示運転」は、外注化によって駅には運転取扱いを行なう労働者が全く居なくなることを前提としたものなのである。
それは運転取扱いに限った話しではない。検修の新保全体系合理化のように、車両や線路、電気、信号通信設備などの検査・保守業務でも、省令改悪-規制撤廃によって、検査のあり方や周期等が、あらかじめ認定を受けた企業は、企業の裁量権で自由に決められるように改悪されている。第二の分割・民営化的な大リストラ攻撃と、運輸省令-運転取扱実施基準の改悪は、どちらが先でどちらが後とも言えない一体のものとして進もうとしている。
「規制緩和」の大合唱が、これまでの鉄道会社のあり方を根本から覆してしまうような大リストラに拍車をかけ、また逆にニューフロンティア21の冒頭にうたわれたような「冷徹な優勝劣敗の市場原理と自己責任の原則に貫かれた真の意味での競争社会が到来している」などという、社会全体を覆う資本の側からのアジテーションがさらに規制撤廃への圧力を増幅させる。---要するに「これだけは守らなければ安全が崩壊する」「これだけは侵してはいけない」という基準、ルールが無くなろうとしているのだ。安全の確保、運転保安の確立という問題にとって、これは恐るべき事態である。
ニューフロンティア21は、その結びで「この改革は当然困難や痛みを伴う」と宣言するが、われわれは今、安全の崩壊という面においても、また労働者の権利、労働条件・雇用・賃金の解体という面においても、重大な分岐点に直面している。
今、「安全の崩壊」という問題はJRばかりでなく日本全体を覆う社会問題となっている。東電の原発事故隠し・検査偽造事件しかり、JOCの核融合事故しかり、雪印食品、日本ハムなど事件しかり、相次いだ原発事故しかり、企業倫理も安全に関する社会的規範も、すべてが崩れ去ろうとしてるかの観がある。
規制緩和と競争原理が社会に蔓延し、安全に直接係わる現場の業務のほとんどが下請け、孫請けにアウトソーシングされ、安全に関する指導やチェック機能が全社会的規模で崩壊しようとしている。JRも同じ道を突っ走り始めたのだ。
しかもこうした流れは、個々の企業の問題というよりも、事故と事故隠しを構造化させるものだ。規制の緩和・撤廃は、本来は企業自身の責任が重くなることを意味する。企業は規制緩和をいいことに安全を徹底して切り捨てるが、その結果事故が起きると、自らの責任回避のために事故隠しに躍起となる。そして隠しきれなければ、事故を起こした当該の労働者に全ての責任をおしきせて、企業としての責任を逃れようとする。
こうしたベクトルがこれまで以上に強まろうとしている。「進行の指示運転」をめぐる事態も全く同じだ。「信号を無視しろ」と指示され、事故が起きれば、今度は企業が責任を逃れるために、その責任は全て運転士におし着せられるのである。
|
|
「場内に対する進行の指示運転」を行う区間について進行の指示は、故障した場内信号機から到着番線停止位置まで一括して指示する。 |
-----------------------------------------------------
だが、今回の取り扱いでは、信号よりも「進行の指示」の方が上位に置かれることになったのだ。
われわれは団体交渉のなかでもこの点を追及したが、JR東日本本社は「進行の指示は信号にあたる」と平然と主張している。また、国土交通省令の解説なかでも「進行を指示する信号の現示と進行の指示とを対等なものとしながら、……」と書かれているのだ。
「進行の指示」には4つの方法・ケースが定められているが、現実には、すでにこの間の合理化攻撃のなかで、多くの駅には駅長や駅長を代務して運転取扱いをすることができる者なおらず、どう考えてもほとんどは指令から無線で指示されることになるのは明らかである。
要するにこれは、無線で指示・通告された場合は信号も無視してそれに従えということだ。無線による指示・通告万能主義である。信号が信号では無くなったのだ。
しかも、JR東日本本社は団交の場で「絶対信号機という概念はない。絶対信号機というのは俗称に過ぎない」とまで言っている。
言うまでもなく、場内・出発を「絶対信号機」としてきたのは、ひとつ間違えば、脱線や衝突など重大事故につながるからである。運転法規に関するJRの指導書でも「主信号機のうち場内信号機、出発信号機は『絶対信号機』と、また閉そく信号機は『許容信号機』と呼ばれる」と明記されてきたことである。それをこのように称してひらき直っているのだ。要するに自らがやろうとしてることに辻つまを合わせるためにこのように言うのだが、それは永年にわたる経緯を無視し、事実にも反した暴論であることは明らかだ。またそれ以前に、本社の安全対策部がこのようなことを平然と口にすること自体、現場の感覚からすれば信じられないものだ。安全に関する感覚が完全に崩壊してしまっているのだ。
しかも国土交通省令では、出発信号機も同様の取り扱いができるとされており、JR東日本も「本来ならば出発信号機もこのような取扱いができるが、今回は場内信号機だけにした」と、ことさに今回は場内だけにしたことを強調している。黙っていれば、いずれ出発信号機にも進行の指示運転が拡大されることは間違いない。
現在は、出発信号機の場合は、代用手信号の現示のみならず、単線区間の場合はすべて、複線区間でも状況によって閉そく方式を変更しなければならないが、もし進行の指示運転が出発信号機まで拡大された場合、こうしたことも含めてどのようになるのか、ぞっとせざるを得ない。ことは深刻なのである。そうなればひとつ間違えばまさに正面衝突だ。
実際、後に触れるように信号に対する考え方を変えてしまった結果、「閉そく」や「防護する区間」という、安全上最も要をなす概念もあいまい化され、崩されてしまったのである。
「進行の指示運転」では、場内信号機の機外で指示を受けた場合、「所定の停止位置まで一括指示する」という取扱いとなり、それがさらに重大な問題を引き起こすことになる。
千葉運転区で配布された資料でも「信号による運転方法ではないので、場内信号機が複数あるときでも、その現示に係わらず指示された番線の停止位置まで運転を行なう」と記載されているように、例えば、第1場内の機外で進行の指示を受けた場合は、第2場内、第3場内はどんな現示であろうと、信号を無視して停止位置まで進行せよという運転取扱いになる。まさに「信号を無視しろ」という指導が日常的に行なわれ、実行されることになるのだ。
この点に関しても本社は、言うにこと欠いて「無視するというのではなく、第1場内、第3場内信号機は見なくていいということだ」と回答した。無視しろというよりもっと悪い。指令から指示を受けた場合は信号を見なくていいというのだ。鉄道の歴史が始まって以来前代未聞の回答である。
だが、第1場内で進行の指示を受けて列車を進めたとする。そのときは第2場内は進行現示だったとしても、何らかの事態が発生して急に停止信号に変わることは充分ありうる話しである。あるいは警戒信号が現示されていたり、違線開通ということもありうる。運転士はその信号現示が目に入ったとしても、見なかったことにして突っ走れというのだ。
しかもここには、「進行の指示は信号にあたる」「代用手信号と同等の位置づけにある」とJRが自ら主張したこととの関係でも明らかな矛盾がある。進行の指示が代用手信号にあたるのだとすれば、閉そく区間はあくまでも第2場内までのはずだ。無視していいなどという根拠は何ひとつないのだ。
また、停止位置までを1閉そく区間とするのであれば、閉そく区間の変更の取り扱いをしなければならないし、運転士にして見れば、停止位置(停止目標)を少しでも出てしまえば、「閉そく違反」という重大事故の責任を着せられかねないことになる。
JRは「閉そく違反とはしない。閉そく区間の変更ではない」としているが、やっていることと言っていることが自己矛盾をきたしている。
要するにJRは、「閉そく」や「防護区間」という最も基本的な概念をつき崩してしまったのである。実際現場で配られている文書には「進行の指示運転は信号機の防護区間にとらわれず、……運転する方法です」などと書かれている。列車の安全確保に関する運転取扱いの基本中の基本が解体されてしまったのだ。
こうした発想は「閉そく指示運転」にも表れている。閉そく指示運転の場合、取扱い自体はこれまでと変更はないが、新国土交通省令では、これまでのように「閉そくによる運転方法の特殊な取扱い」ではなく、新たに「運転士の注意力による運転方法」として位置づけられている。
JRはこれを「(運転士の注意力による運転が)閉そくによる運転と同等の、一運転方法として確立されたものである」と解説している。これはとんでもないことだ。運転士の注意力による運転なるものが、閉そく方式と同等の運転方法だというのである。こんな発想が拡大解釈されたら恐るべきことになりかねない。
しかもこれにより、運転方法が、①閉そくによる方法、②進行の指示による方法、③運転士の注意力による方法と、3種類も定められたことになる。
「進行の指示運転」は、さらに重大な問題点をもっている。先に触れたように、指示の方法は、①CTC指令が無線で指示する場合、②駅長等が指示書で指示する場合、③駅長等が構内無線で指示する場合、④駅長等が指令を介して無線通告する場合の4つのケースが定められているが、これに加え、⑤代用手信号による方法、⑥誘導による方法を加えれば、これだけでも、場内信号機故障時の取扱いに6つものケースが存在することになる。
しかも実際はそればかりではないのだ。「手信号代用器」が設置されている駅については、さらに3つのケースが存在することになる。
さらには、①千葉駅での佐倉方から千葉駅に進入する場合の上り第2場内信号機、②総武緩行線西千葉駅から千葉駅に進入する場合の第1場内信号機、③二俣支線・高谷支線の1RA・5L・6LF・10R及び、総武快速B線、市川-新小岩間にある30LWは、「進行の指示運転」を行なわない、④いわゆる構内閉そく信号機(新浦安・市川塩浜・二俣新町)は場内に対する進行の指示と同様の取扱いをする、という「特殊な取扱い」が存在し、⑤車内信号区間の場合、「東京駅の第1閉そく進路内では、場内冒進が考えられるのため基本的には行なわない。ただし、これを越えて運転する必要があるときは、指令が場内進路標識が見える箇所まで運転を指示する」(千葉運転区で配布された教育資料)とされている。
また、JR貨物の職場では、このような「特殊な取扱い」が存在すること自体、全く知らされてもいない。
こうしたことに加え、千葉支社では本社の回答はくつがえされたが、同じ場内信号機故障でも、代用手信号による場合は進行できるのは第2場内までであるのに、「進行の指示」だった場合は停車場の所定停止位置までとなるという混乱の要素まである。
まさに複雑怪奇としか言いようのないものとなったのである。率直に言って、運転士がこうしたことを全て明確に記憶しつづけることなど不可能に近いことだ。実際、教育・訓練が行なわれたばかりの現時点ですら、こうしたことを全て理解できている運転士や駅の係員はほとんど居ないといっていい。それどころか、指導員や指令員、支社の幹部ですら大差ない状態だ。
こんなことを教育され場合、運転士の記憶に残るのは、「信号機が故障していようが停止現示だろうが、指令や駅から何か言われたら、とにかく列車を動かさなければならない」ということだけになるのはごく自然な流れに他ならない。これが1年経ち、3年経ち、5年経ったらどうなるのか。またこれまでのように「絶対信号機」という教育を受けた世代がいなくなり、初めからこのような教育だけを受けた世代になったらどうなるのか、恐ろしいことだ。
しかも、場内信号機故障などの異常時に遭遇した場合、運転士や指令員は多かれ少なかれパニックになる。
大月駅の事故などはその典型だが、冷静に考えれば絶対にやってはならないことをやってしまうのが、異常時に遭遇したときの運転士の心理である。こんな複雑なことを決めるということは、「事故を起こせ」と言っているに等しいことだ。
実際、「閉そく指示運転」のような単純な取扱いでも、他の列車の無線を聞いていた運転士が行っていいものだと思い込んで、指令の指示を受けないまま閉そく信号機を越えてしまうという事故が千葉支社管内で発生しているのだ。
また、JR貨物では「特殊な取扱い」などは、未だ運転士には全く教育すらされておらず、運転士は誰ひとり知らないのが現状だ。JR東日本のなかでも、「特殊な取扱い」の一部(京葉線内)は、実施の数日前になって、千葉-東京の支社間で調整ができていなかったことが発覚して、掲示一枚で、「当面従来の運転取扱いを行なう」ということで出発せざるを得ない状態であった。
要するにこれは、「場内に対する進行の指示運転」なる取扱いが根本的に間違っているということ、無理に無理を重ねて、とにかく列車を進めろという発想だけが先行したために、現実の場面では決定的な矛盾が噴きだしていることを示している。
運転取扱い等の規程にとって、最低必要かつ最も重要な条件は、
① 何よりも、人間の判断は完全ではないことや保安装置等の動作も異常をきたすことがあることを前提として、それでも安全が確保できること。
② 単純明快であること。
の2点である。このいずれの点からしても、「進行の指示運転」は、運転取扱いに関する定めとしての体をなしていないと言わざるをえない。
問題点は他にも数多くある。「進行の指示運転」では、無線による指示ひとつで、ATSの開放運転が公然と指導されるようになった。故障した信号機ごとにATS-SNのNFBを切り、あるいはATS-Pのブレーキ開放スイッチを取り扱って、保安装置が全く無い状態で運転することになるのである。
ATSのNFBスイッチは、1997年の大月駅事故の後、その対策として、安易に切ることはできないように封印されることになった。
だが会社は、「喉元を過ぎれば熱さを忘れる」かのように、無線による指示ひとつでその封印を破って開放扱いをしろ、ということを教育し始めたのである。
場内信号機故障時という、最も事故の起きる可能性の高い輸送混乱時・異常時に、場内という列車衝突も含む重大事故が起きる可能性が最も高い箇所で、無線ひとつでATSを切れ、と指示するほど危険なことはない。要するに「安全よりも効率優先」「とにかく列車を走らせろ」「駅も徹底的に合理化する、駅員が居るなどと思うな」「指令から無線で指示を受けたら何でも従え」---これが一切なのである。
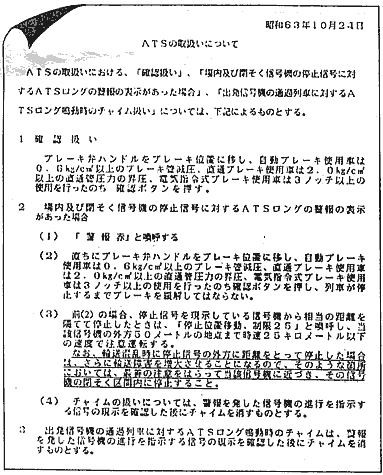
ポイント鎖錠の考え方が変えられたことも問題だ。これまで場内信号機が故障として代用手信号を用いる場合は、駅係員が関係転てつ器を鎖錠しなければ、列車を動かすことができなかった。
しかし「進行の指示運転」の導入に伴って「電気的鎖錠」などという考え方が規程にもち込まれた。「電気的鎖錠」とは、連動装置の制御盤やCTC制御盤などで、軌道回路表示灯(ラインライト)の表示があれば、電気的に鎖錠されていると見なすということである。これまでのように、現場でポイントを機械的に鎖錠する必要はないということだ。
だが、制御盤での確認だけで本当にポイントが鎖錠されている称することができるのか。制御盤の故障などでポイントの開通と「ラインライト」の表示がくい違う可能性は100%ゼロだと言えるのか。CTC指令などが制御盤を見るだけで「鎖錠」と称したときに、確認ミスの発生などはどう防ぐのか。ミスがあったときに運転士の責任はどうなるのか。疑問点が次々と湧いてこざるを得ない。
さらに「進行の指示」を受けた場合の速度制限が「関係するポイント45㎞/h以下」とされたことも問題だ。
速度規制は「閉そく指示運転」(無閉そく運転)でも15㎞/h以下である。危険度は、場内信号機が故障した状態のなかで列車を場内に進行させることの方が格段に高い。しかし「関係するポイント45㎞/hだといのだ。ポイントを過ぎれば速度は無制限である。
会社は「代用手信号と同等の位置づけによる運転だから45㎞/hで構わない」としているが、これまで述べてきたように、前提条件が全く違うのである。代用手信号の場合は、駅員が直接進路を確認し、ポイントを鎖錠し、信号をだすのであり、しかも進行できるのは第2場内までである。あまりの暴論と言うしかない。
ちなみに会社は、「閉そく指示運転も、国土交通省令上は40㎞/h以下で良いことになっているが、JR東日本は15㎞/h以下としている」と、安全サイドにたった対応をしているかのように言っている。
だが、そんなことをしたら間違いなく東中野事故の再来となる。
1988年の東中野事故は、場内及び閉そくの停止信号に対するロングの警報を受けた場合の取扱いについて、「輸送障害を増大させることになるので、最善の注意をはらって当該信号機に近づき、その信号機の閉そく区間内に停止すること」という指示文書を千葉支社がだしたことによって起きたものだ。千葉支社は、「輸送障害を増大させないために、停止信号を越えてから止めろ」というとんでもない指示をしたのである。
その結果起きたことは、列車衝突によって、乗客と平野運転士2名の尊い生命が奪われるという痛ましい事故であった。
この指示文書は事故の後、こっそりと撤回され、別の指示文書に差し替えられたが、「進行の指示運転」は、本質的にはこれと同じ、否もっとひどい指示だと言わざるを得ない。
「進行の指示運転」や 「閉そく指示運転も40㎞/hでもいい」などという主張は、東中野事故を再び起こせと言うに等しいものである。
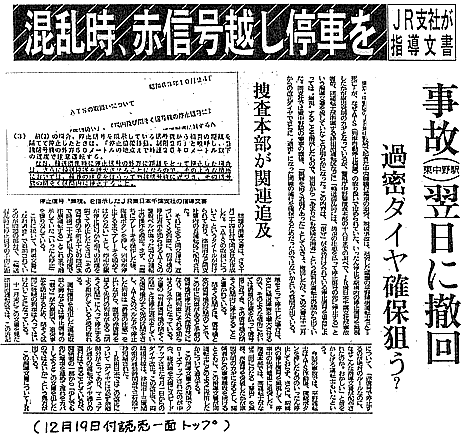
|
|
| 進行の指示を受けて列車を進行させた場合、列車が動きだしてから所定の停止位置に停止するまで、例えどのようなことがあろうと運転士の責任とはしない。 |
何よりも昨年来、全力をあげて「進行の指示運転」に関する問題点を本社・支社・現場で追及し、闘いを展開してきた大きな成果として、千葉支社をここまで追いつめたことを、大きな成果として確認することができる。
しかし、問題はこれで解決したわけではない。「進行の指示運転」そのものが問題なのだ。冒頭に触れたようにこの取扱いは、安全に係わる運転取扱いの最も基本の部分=信号絶対主義を解体するものである。だからわれわれは、あくまでも「進行の指示運転の即時中止」を求めてさらに闘いを強化しなければならない。
さらには、千葉支社は「例えいかなることがあろうと運転士の責任にはしない」と回答したが、例えば運転士の刑事責任が問われるような重大事故が発生した場合、この団交での確認は本当に約束どおり貫かれるのか、現在のJRの経営姿勢を考えた場合、重大な疑念が残らざるを得ない。疑念どころか。結局は運転士の責任に帰せられることは火を見るよりも明らかだと言わざるを得ない。
それ以前に、いくら「運転士の責任にはしない」などと言っても、東中野事故のように、乗客や運転士の生命が奪われるような悲惨な事故に行き着いてしまってからでは、何を言おうが何の意味もない。
やはりわれわれの基本的な立場は、「闘いなくして安全なし」---以外にはあり得ないのだ。
|
|
| 責任追及から原因究明へという方向を明確に示し得たJR東日本の経営幹部は立派だ。世界に冠たる資質をもっている。責任追及が原因究明に転化したということは
、経営哲学あるいは企業文化の極めて高いレベルの所産だ。 責任追及から原因究明へという世界に冠たるテーマ、概念、カテゴリーを明確にし得たJR東日本の労使の高いレベルをこれからも誇りにしていきたい。 (第10回政策フォーラム) |
この言い方はあまりに異様だ。新興宗教の教団が教祖を崇めたてるかのように会社を讃え、結局は会社への奴隷的な忠誠を誓っているのである。
しかもこの発言が、97年10月に起きた大月駅事故の1ヵ月後に行なわれていることを考えればなおさら異常としか言いようがない。
事故当該の東労組組合員は、逮捕されて連日警察の取り調べを受けており、マスコミですら「JRの指導体制には背筋が凍る思いだ」(朝日新聞)等、安全に関するJR東日本の指導体制の問題点を厳しく追及していた状況の最中で、松崎は平然とこのような発言をしていたのだ。
しかも機関紙などでは、事実関係が明らかになる前から、「事故は本人のミスによるものだ」と、繰り返し繰り返し書き立てたのである。東中野事故で自らの組合員が死亡したときも同じであった。
意図は明らかだ。組合員を犠牲にしようが、安全を犠牲にしようが、とにかく会社と革マルの結託体制を守るという、ただ一点だけを念頭に、このような発言を繰り返したのである。事故を起こしたくて起こす労働者はひとりもいない。組合員が不幸にして事故に遭遇し、警察に逮捕されたとき、その組合員を守ろうとしない労働組合は労働組合ではない。
「進行の指示運転」で、貝のように黙んまりを決め込んだのも、全く同じ意図である。一体これが労働組合と言えるのか。絶対に否である。
そもそも、東労組・革マルが繰り返している「責任追及から原因究明へ」なるスローガン自体が、職場の現実を知っている者ば誰でもわかるとおり、全くのペテンに他ならない。
東労組のこのスローガンは、労働者への責任追及をさせないということではなく、「事故や安全問題について会社の経営責任の追及は絶対にしません」という表明に他ならない。
東労組・革マルは、JR西日本や東海で起きた事故については、社宅へのビラまきなど「追及行動」を行なうが、東日本で起きた事故については一度たりと追及したためしがない。要するに彼らは、安全や運転保安のことなど、何ひとつ真剣に考えてはいないということである。彼らにとって安全問題とは、革マルに従わない者を追及する政治的な道具に過ぎないのだ。まさに労働者とは全く無縁の腐りきった存在だ。
|
|
| 1. 通告受領券はすべて列車の停止時に受け取ること。 2. 走行中に通告受領券の指示を受けた場合は直ちに停止すること。 3. 通告については、その場で「受領券」に記入すること。 4. 走行中に運転台を離れなければならない事態(列番設定の確認依頼等)が発生したときは直ちに停止措置をとりこと。 5. それぞれ停止措置をとったときは、指示に連絡を行こなうだけで、許可は必要ない。 6. 通告受領券は必ず当直に提出すること。 |
疑問や問題のある指令からの指示・通告を受けたとき、聞いたときは、全て支部に通告を!
| 03春闘 ストライキ | |||
|
3月27日(木) |
3月28日(金) | 3月29日(土) | 3月30日(日) |
| 初日 |
2日目 03春闘勝利 スト貫徹 動労千葉総決起集会/(午後1時、千葉県労働者福祉センター) |
3日目 春闘総行動 3・29 03春闘勝利! 労働者集会(代々木公園)へ |
最終日 三里塚3・30全国総決起集会へ参加 |
| ストライキを決行! | 400名の結集で集会と支社デモを闘う | 1600名の参加で集会とデモ | 労農国際連帯 |
|
|
|||